こんにちは、管理人のdoggoです
愛犬が年を重ね、シニア期に入ると、これまで当たり前にできていたトイレがうまくいかなくなることがあります。
粗相が増えたり、まったく違う場所でしてしまったりと、老犬がトイレでしない姿に戸惑い、悩んでいる飼い主さんも多いのではないでしょうか。
しかし、それは決して犬のわがままや、しつけの失敗ではありません。
老犬がトイレでしない背景には、筋力の低下や認知症といった加齢による変化、何らかの病気やストレスなど、様々な原因が隠れている可能性があります。
この記事では、まず考えられる原因を深掘りし、病気のサインや認知症の初期症状について解説します。
そのうえで、具体的な対策としてすぐに実践できる環境改善のアイデアや、精神的なストレスを和らげるためのしつけのポイント、おむつの上手な活用法などを紹介します。
また、動物病院に相談すべきタイミングや、伝えるべき情報についても触れていきます。
愛犬の変化に寄り添い、穏やかなシニアライフをサポートするために、一緒に原因と対策を学んでいきましょう。
◆このサイトでわかる事◆
- 老犬がトイレでしなくなる主な原因
- トイレの失敗に隠された病気のサイン
- 認知症とトイレ問題の関係性
- 今日からできるトイレ環境の改善策
- 老犬のストレスを減らす接し方
- おむつや介護グッズの上手な使い方
- 動物病院に相談する適切なタイミング

愛犬の「食べない」に終止符を。手作り食レシピから生まれた『モグワン』
「せっかく買ったフードを食べてくれない…」そんな悩みを抱えていませんか?
『モグワン』は、愛犬の健康と食いつきの良さをとことん追求し、家庭での手作りごはんをヒントに誕生したプレミアムドッグフードです。
【モグワンが選ばれる3つの理由】
- 動物性タンパク源50%以上:新鮮なチキンとサーモンを贅沢に使用。封を開けた瞬間の香りが、愛犬の食欲を刺激します。
- 究極のグレインフリー:消化に負担をかける穀物を一切使わず、お腹にやさしいレシピを実現しました。
- ヒューマングレードの原材料:人間が食べる食材と同等の高品質な素材を厳選。着色料や香料も不使用で安心です。
毎日のごはんは、愛犬の体を作る大切な基盤。 「美味しそうに完食する姿が見たい」という飼い主さんの願いを、モグワンが叶えます。
今なら公式サイト限定の特別キャンペーンも実施中!まずは愛犬の驚くべき「食いつき」を体験してみませんか?
老犬がトイレでしない5つの原因と病気の可能性
◆この章のポイント◆
- 筋力の低下や身体機能の衰え
- トイレの場所が分からない認知症の始まり
- 環境の変化によるストレスを感じている
- 泌尿器系の病気が隠れているサインかも
- 関節の痛みで排泄の姿勢が辛い
筋力の低下や身体機能の衰え
老犬がトイレでしない最も一般的な原因の一つが、加齢に伴う筋力や身体機能の低下です。
若い頃は当たり前にできていた動作が、シニア期になると難しくなり、トイレの失敗につながることがあります。
具体的には、足腰の筋力が衰えることで、いくつかの問題が生じます。
まず、トイレまで我慢する力が弱くなります。
膀胱や腸の括約筋も筋肉の一部であるため、その機能が低下すると尿意や便意を感じてからトイレに間に合わず、途中で漏らしてしまうことが増えるのです。
また、踏ん張る力が弱くなることも原因となります。
特に排便時には、腰を落としてぐっと力を入れる必要がありますが、後肢の筋力が衰えているとこの姿勢を維持するのが困難になります。
そのため、排便をためらったり、途中でやめてしまったり、あるいは歩きながら排泄してしまったりすることがあります。
さらに、寝たきりの時間が長くなることも影響します。
自分で起き上がってトイレに行くことが難しくなると、寝床の近くで粗相をしてしまうケースが増えます。
これは犬自身の意思とは関係なく、身体が思うように動かないために起こる現象です。
視力や嗅覚の衰えも、トイレの失敗に関係しています。
犬は元々、決まった場所の匂いを頼りにトイレを覚えますが、嗅覚が鈍くなるとトイレシーツの場所を正確に認識できなくなることがあります。
同様に、視力が低下すると、トイレの場所が見えにくくなり、見当違いの場所で排泄してしまうことも少なくありません。
これらの身体的な衰えは、犬自身にとってもどかしく、不安なものです。
決してわざとやっているわけではないため、飼い主さんはその変化を理解し、根気強くサポートしてあげることが重要になります。
例えば、トイレまでの動線を短くしたり、滑りにくい床材に変えたりするだけでも、犬の負担を大きく軽減できるでしょう。
加齢による変化は避けられませんが、環境を整えることで、犬の尊厳を保ちながら快適な生活を送れるように手助けすることが求められます。
トイレの場所が分からない認知症の始まり
老犬がトイレでしない原因として、犬の認知症(認知機能不全症候群)の可能性も考えられます。
人間の認知症と同様に、犬も高齢になると脳の機能が低下し、様々な行動の変化が見られるようになります。
トイレの失敗は、その代表的な初期症状の一つです。
認知症を発症すると、これまで覚えていたトイレの場所を忘れてしまうことがあります。
「どこで排泄すれば良いのか分からない」という混乱から、部屋の隅や家具の陰など、思いがけない場所で粗相をしてしまうのです。
また、自分が今何をしているのか分からなくなり、排泄の途中で歩き出してしまったり、食後すぐにトイレに行くという習慣を忘れてしまったりすることもあります。
認知症によるトイレの失敗には、いくつかの特徴的なサインが見られます。
- これまで一度も失敗したことがない場所で、頻繁に粗相をするようになった。
- 飼い主がトイレに誘導しても、そこがトイレだと認識できない様子を見せる。
- ソワソワと落ち着きなく歩き回った末に、突然その場で排泄してしまう。
- 夜鳴きや昼夜逆転の生活など、トイレ以外の行動にも変化が見られる。
特に、目的もなく部屋をウロウロする、狭い場所に入り込んで動けなくなる、飼い主の呼びかけへの反応が鈍くなるといった行動が同時に見られる場合は、認知症の可能性がより高まります。
認知症は進行性の病気であり、残念ながら完治させることはできません。
しかし、早期に発見し、適切なケアを行うことで、進行を緩やかにし、愛犬の生活の質(QOL)を維持することは可能です。
もし認知症が疑われる場合は、自己判断せずに、まずは動物病院で獣医師の診断を受けることが不可欠です。
獣医師は、行動学的評価や他の病気の除外診断を通じて、総合的に判断します。
診断が下された場合、脳の血流を改善するサプリメントや、不安を和らげる薬などが処方されることもあります。
家庭では、犬が混乱しないように家具の配置をなるべく変えず、トイレの場所を分かりやすく示すなどの工夫が求められます。
トイレシーツを広く敷き詰めたり、犬が多くの時間を過ごす寝床の近くにもトイレを設置したりすることで、失敗を減らすことができるでしょう。
認知症のケアは長期戦になりますが、飼い主さんの愛情深いサポートが、愛犬の穏やかな老後につながります。
環境の変化によるストレスを感じている
犬は非常に繊細な動物であり、環境の変化に敏感に反応します。
特に老犬になると、適応能力が低下し、些細な変化でも大きなストレスを感じることがあります。
そして、そのストレスが原因で、老犬がトイレでしないという問題行動につながることが少なくありません。
ストレス性のトイレの失敗は、精神的な不安や混乱から生じます。
犬がストレスを感じる原因は多岐にわたります。
例えば、以下のような出来事が引き金になる可能性があります。
生活環境の変化
引っ越しや部屋の模様替え、家具の配置変更などは、犬にとって大きな環境変化です。
これまで安心できる場所だったテリトリーの様子が変わることで、混乱し、トイレの場所が分からなくなったり、不安から粗相をしてしまったりします。
家族構成の変化
新しいペットを迎える、赤ちゃんが生まれる、家族の一員が進学や就職で家を出るなど、家族構成の変化もストレスの原因になります。
特に、新しいペットに対して嫉妬や縄張り意識を感じ、飼い主の注意を引くためにわざと粗相をする「マーキング」のような行動が見られることもあります。
留守番時間の増加
飼い主のライフスタイルの変化により、留守番の時間が長くなることも、犬にとっては大きなストレスです。
分離不安を抱えている犬の場合、飼い主がいない寂しさや不安から、トイレ以外の場所で排泄してしまうことがあります。
大きな音や騒音
家の近くでの工事の音や、雷、花火の音なども、聴覚が敏感な犬にとっては強いストレス源です。
恐怖心からパニックになり、トイレに行く余裕がなくなってしまうことがあります。
これらのストレスサインを見逃さず、原因を特定し、できる限り取り除いてあげることが重要です。
もし環境の変化が避けられない場合は、犬が安心できるスペースを確保してあげましょう。
例えば、愛犬が好んで使っているベッドやおもちゃを置いた静かな場所を用意し、そこが安全な避難場所であることを教えてあげます。
また、飼い主とのコミュニケーションの時間を増やすことも、犬の不安を和らげるのに役立ちます。
優しく声をかけたり、体を撫でてあげたりすることで、犬は安心感を得ることができます。
トイレの失敗を叱ることは、犬のストレスをさらに増大させるだけなので、絶対に避けるべきです。
根気強く、愛情を持って接することで、犬は少しずつ新しい環境に慣れていくでしょう。
泌尿器系の病気が隠れているサインかも
老犬がトイレでしない、あるいは頻繁に失敗するようになった場合、単なる老化現象と片付けずに、病気の可能性を疑うことが非常に重要です。
特に、泌尿器系の病気は排泄行動に直接影響を与えるため、注意深い観察が求められます。
トイレの失敗がサインとなる代表的な病気には、以下のようなものがあります。
膀胱炎
細菌感染などによって膀胱に炎症が起こる病気です。
膀胱炎になると、頻尿(何度もトイレに行く)、残尿感(排尿後もスッキリせず、ポタポタと尿が漏れる)、血尿などの症状が見られます。
強い尿意を常に感じるため、トイレまで我慢できずにその場で漏らしてしまうことが増えます。
排尿時に痛みを伴うため、キャンと鳴くこともあります。
尿路結石症
腎臓、膀胱、尿道などに結石ができる病気です。
結石が膀胱や尿道を刺激することで、膀胱炎と同様に頻尿や血尿といった症状を引き起こします。
結石が尿道に詰まってしまうと、尿が出なくなる「尿道閉塞」という危険な状態に陥ることもあり、命に関わるため緊急の対応が必要です。
腎臓病
腎臓の機能が低下する病気で、老犬に非常に多く見られます。
腎臓は体内の老廃物をろ過し、尿として排出する役割を担っていますが、その機能が衰えると、薄い尿を大量に作るようになります。
これを「多飲多尿」と呼び、水をたくさん飲み、おしっこの量と回数が著しく増えるのが特徴です。
膀胱に尿が溜まるスピードが速いため、トイレの失敗が目立つようになります。
クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)
副腎からコルチゾールというホルモンが過剰に分泌される病気です。
この病気も腎臓病と同様に、多飲多尿の症状を引き起こすことが知られています。
その他、食欲増進、腹部膨満、脱毛などの症状を伴うことがあります。
これらの病気は、放置すると犬の体に大きな負担をかけ、重篤な状態につながる可能性があります。
もし、トイレの失敗と共に「水を飲む量やおしっこの量が異常に増えた」「尿に血が混じっている」「排尿時に痛そうにしている」「元気や食欲がない」といった他の症状が見られる場合は、できるだけ早く動物病院を受診してください。
獣医師による尿検査や血液検査、超音波検査などによって、正確な原因を突き止め、適切な治療を開始することが、愛犬の健康を守るために不可欠です。
関節の痛みで排泄の姿勢が辛い
老犬がトイレでしない原因として、見過ごされがちながら非常に多いのが、関節の痛みです。
特に大型犬や肥満傾向の犬に多く見られる変形性関節症や、犬種によっては遺伝的にかかりやすい股関節形成不全などが、排泄行動に大きな影響を与えます。
犬が排泄する際には、特定の姿勢をとる必要があります。
排尿時には後肢を少し曲げ、排便時にはさらに深く腰を落として踏ん張る姿勢をとります。
しかし、関節に痛みや炎症があると、この一連の動作が激しい苦痛を伴うようになります。
そのため、犬は痛みから逃れるために、排泄そのものを我慢しようとしたり、楽な姿勢で済ませようとしたりします。
結果として、以下のようなトイレの失敗につながります。
- 排便を我慢してしまい、便秘になる。
- 痛みの少ない場所を探して歩きながら排泄してしまう。
- 踏ん張ることができず、トイレシーツの外にはみ出してしまう。
- トイレシーツなどの段差をまたぐこと自体が苦痛で、トイレに行くのを嫌がる。
関節の痛みを抱えている犬は、トイレ以外にも様々なサインを出しています。
例えば、「散歩に行きたがらない」「階段の上り下りを嫌がる」「寝ている状態から立ち上がるのに時間がかかる」「体を触られるのを嫌がる」といった行動の変化が見られたら、関節に問題がある可能性が高いです。
犬は痛みを言葉で伝えることができないため、飼い主がこれらの小さな変化に気づいてあげることが非常に重要です。
もし関節の痛みが疑われる場合は、動物病院で相談しましょう。
獣医師は触診やレントゲン検査によって状態を評価し、痛みを和らげるための消炎鎮痛剤や、関節の健康をサポートするサプリメントなどを処方してくれます。
家庭でのケアも痛みの緩和に役立ちます。
体重管理は関節への負担を減らすために最も重要です。
また、滑りにくい床材に変える、段差にスロープを設置する、クッション性の高いベッドを用意するなど、生活環境を整えることも効果的です。
トイレの場所も、犬が楽に排泄できるような工夫を凝らしましょう。
例えば、体を支えられるように壁際にトイレを設置したり、踏ん張りが効くように足元に滑り止めマットを敷いたりするだけでも、犬の負担は大きく変わります。
痛みが和らげば、トイレの失敗も自然と改善されることが期待できます。
老犬がトイレでしない場合の具体的な対策としつけ
◆この章のポイント◆
- トイレの環境改善で失敗を減らす
- 生活リズムを整えて排泄を促す
- 粗相をしても叱らないことが大切
- おむつやマナーウェアを上手に活用する
- かかりつけの動物病院に相談する
- 老犬がトイレでしない悩みと向き合いサポートしよう
トイレの環境改善で失敗を減らす
老犬がトイレでしない問題に対応する際、まず最初に取り組むべき最も効果的な対策が、トイレ環境の見直しです。
加齢によって身体能力が低下した愛犬にとって、若い頃と同じトイレ環境では使いにくくなっている可能性があります。
少しの工夫で、犬の負担を減らし、トイレの成功率を格段に上げることができます。
トイレの場所を見直す
老犬になると、寝ている時間が長くなり、トイレまでの移動が億劫になったり、間に合わなくなったりします。
愛犬が普段多くの時間を過ごす寝床やリビングのすぐ近くにトイレを設置してあげましょう。
場合によっては、複数箇所にトイレを用意することも有効です。
「トイレに行きたい」と思ったときに、すぐに行ける環境を作ることが大切です。
トイレの範囲を広げる
視力の低下や足腰の衰えにより、トイレシーツの範囲内に正確に排泄することが難しくなります。
トイレトレーの周りにもトイレシーツを敷き詰め、トイレ全体の面積を広くしてあげましょう。
どこで排泄してもシーツの上になるように、広範囲をカバーすることで、「惜しい失敗」を防ぐことができます。
ペット用の防水マットなどを下に敷くと、掃除の手間も省けます。
段差をなくす
市販のトイレトレーには縁に段差があるものがほとんどですが、老犬にとっては、このわずかな段差をまたぐことさえ負担になることがあります。
関節に痛みがある場合はなおさらです。
トレーの使用をやめ、トイレシーツを直接床に敷くだけのフラットなトイレに変更するだけでも、犬は楽に排泄できるようになります。
もしシーツのずれが気になる場合は、滑り止めシートの上に敷くと良いでしょう。
滑らない工夫をする
フローリングなどの滑りやすい床は、足腰の弱った老犬にとって非常に危険です。
踏ん張りが効かずに滑ってしまうと、排泄の姿勢がとれなかったり、転倒して怪我をしたりする恐れがあります。
トイレの周りや、寝床からトイレまでの動線には、コルクマットや滑り止め効果のあるカーペットなどを敷きましょう。
これにより、犬は安心してトイレに向かい、しっかりと踏ん張って排泄することができます。
明るさと清潔を保つ
視力が低下している犬のために、トイレの周りは明るく保ち、場所を認識しやすくしてあげてください。
また、犬はきれい好きな動物なので、汚れたトイレでは排泄したがらないことがあります。
トイレシーツはこまめに取り替え、常に清潔な状態を維持するよう心がけましょう。
これらの環境改善は、どれもすぐに始められることばかりです。
愛犬の現在の身体状況をよく観察し、何がトイレの妨げになっているのかを見極め、最適な環境を整えてあげることが、問題解決への第一歩となります。
生活リズムを整えて排泄を促す
トイレの環境改善と並行して行いたいのが、生活リズムを整え、排泄のタイミングを飼い主が管理し、サポートしてあげることです。
犬の体は非常に規則正しく機能しており、毎日決まった時間に食事や散歩をすることで、排泄のリズムもおのずと整ってきます。
老犬になると、尿意や便意を感じる感覚が鈍くなることがあるため、飼い主が積極的にトイレに誘導してあげることが、粗相の防止につながります。
排泄のタイミングを把握する
まずは、愛犬がどのようなタイミングで排泄しているかを記録し、パターンを把握することから始めましょう。
犬が排泄しやすいタイミングは、一般的に以下の通りです。
- 朝、目が覚めた直後
- 食事の後
- 水を飲んだ後
- 遊んだり興奮したりした後
- 寝る前
これらのタイミングで、優しく声をかけながらトイレの場所まで連れて行ってあげましょう。
最初は戸惑うかもしれませんが、これを習慣化することで、犬は「この時間になったらトイレだ」と学習し、自然と排泄できるようになります。
排泄のサインを見逃さない
犬は排泄したくなる前に、特有のサインを見せることがあります。
床の匂いをクンクン嗅ぎながらウロウロ歩き回る、ソワソワと落ち着きがなくなる、クルクルとその場で回るなどの行動は、トイレを探しているサインです。
このサインを見つけたら、すぐさまトイレに誘導しましょう。
タイミング良く成功体験を積ませることで、犬は再びトイレの場所を思い出すことができます。
食事の時間を一定にする
食事の時間を毎日同じにすることで、消化と排便のリズムが安定します。
特に便は、食後数時間以内に出ることが多いため、食事時間を固定すれば、排便のタイミングも予測しやすくなります。
老犬用の消化の良いフードを選ぶことも、胃腸への負担を減らし、安定した排便につながります。
寝る前のトイレを習慣に
夜間の粗相を防ぐために、飼い主が寝る前に必ず一度トイレに連れて行く習慣をつけましょう。
たとえ犬が寝ていても、優しく起こしてトイレを促します。
これにより、膀胱を空にしてから眠りにつくことができ、夜中に漏らしてしまうリスクを減らすことができます。
生活リズムを整えることは、根気のいる作業ですが、トイレトレーニングの基本に立ち返るつもりで、焦らずじっくりと取り組みましょう。
飼い主が愛犬の体のリズムを理解し、それに合わせてサポートすることで、トイレの悩みは着実に改善していくはずです。
粗相をしても叱らないことが大切
愛犬が粗相をしてしまったとき、つい感情的に「ダメでしょ!」と叱りつけてしまう飼い主さんは少なくありません。
しかし、老犬がトイレでしない問題において、叱るという行為は百害あって一利なしです。
むしろ、問題をさらに悪化させてしまう可能性があることを、強く認識する必要があります。
老犬の粗相は、多くの場合、わざとやっているわけではありません。
筋力の低下で間に合わなかったり、病気でコントロールできなかったり、認知症で場所が分からなかったりと、犬自身にもどうしようもない理由があるのです。
そんな状況で飼い主に叱られると、犬は大きな混乱と恐怖を感じます。
「排泄すること自体が悪いことなんだ」と誤って学習してしまうと、以下のような悪循環に陥る可能性があります。
隠れて粗相をするようになる
飼い主の見ていない場所、例えば家具の裏や押し入れの中など、見つかりにくい場所を選んで排泄するようになります。
これは、叱られるのを避けるための行動であり、問題の発見が遅れ、不衛生な状態を招く原因となります。
排泄を我慢するようになる
排泄すると叱られると学習した犬は、ギリギリまで我慢しようとします。
その結果、膀胱炎や便秘など、新たな健康問題を引き起こすリスクが高まります。
飼い主との信頼関係が崩れる
大好きで信頼している飼い主から、自分の生理現象を叱責されることは、犬にとって深い心の傷となります。
飼い主に対して恐怖心や不信感を抱くようになり、良好な関係性が損なわれてしまいます。
粗相を見つけても、決して騒いだり叱ったりせず、冷静に対応することが鉄則です。
犬を別の部屋に移動させ、何も言わずに黙々と後片付けをしましょう。
掃除をする際は、匂いが残らないように、ペット用の消臭スプレーやクエン酸水、酵素系の洗剤などを使うのが効果的です。
アンモニア臭が残っていると、犬はそこを再びトイレの場所だと認識してしまうため、徹底的に匂いを消すことが重要です。
もし、たまたまトイレシーツの上で上手に排泄できた場面に遭遇したら、その時は大いに褒めてあげてください。
「えらいね」「上手だね」と優しい声で褒め、おやつを少し与えるのも良いでしょう。
「ここで排泄すると良いことがある」というポジティブな経験を積み重ねることで、正しい場所での排泄を再学習する助けとなります。
老犬の介護は、飼い主の精神的な負担も大きいですが、愛犬が安心して暮らせるように、寛大な心で受け止め、穏やかに接してあげることが何よりも大切です。
おむつやマナーウェアを上手に活用する
様々な対策を試みても、加齢や病気によってどうしてもトイレの失敗が減らない場合、犬用のおむつやマナーウェア(マナーベルト)の活用を検討するのも一つの有効な手段です。
おむつに対して「かわいそう」「最終手段」といったネガティブなイメージを持つ飼い主さんもいるかもしれませんが、正しく使えば、犬と飼い主双方の負担を大きく軽減してくれる頼もしい介護グッズになります。
おむつを使用するメリット
- 部屋の汚れを防ぎ、掃除の手間が格段に減る。
- 飼い主の精神的なストレスが軽減され、犬に優しく接する余裕が生まれる。
- 粗相を気にして行動を制限することなく、犬が室内で自由に過ごせる。
- 通院やお出かけの際に、粗相の心配をしなくて済む。
特に、寝たきりの犬や、夜間の無意識な失禁が続く場合には、おむつは非常に役立ちます。
飼い主の睡眠時間を確保し、介護疲れを防ぐためにも、積極的な利用をおすすめします。
おむつ選びと使用上の注意点
おむつを快適に使うためには、いくつかの重要なポイントがあります。
まず最も大切なのが、サイズ選びです。
サイズが合っていないと、隙間から尿が漏れてしまったり、犬が不快に感じて自分で脱ごうとしたりします。
メーカーの体重目安や胴回りのサイズ表を参考に、愛犬にぴったり合ったものを選びましょう。
次に、皮膚のトラブルを防ぐためのケアです。
おむつの中は湿気がこもりやすく、長時間そのままにしておくと、おむつかぶれや皮膚炎の原因となります。
排泄したらできるだけ早く交換し、その都度、濡らしたタオルやペット用のおしりふきで優しく拭いて、皮膚を清潔に保つことが不可欠です。
特に夏場や皮膚の弱い犬の場合は、こまめなチェックが必要です。
また、おむつを嫌がる犬もいます。
最初は短い時間から慣らし、装着できたらたくさん褒めておやつをあげるなど、おむつに良いイメージを持たせる工夫をしましょう。
おむつを固定するためのサスペンダーや、おむつと併用するマナーパッドなど、便利な補助グッズも市販されているので、状況に応じて活用すると良いでしょう。
おむつは、あくまでトイレの失敗をカバーするための補助的なツールです。
おむつをしているからといって、トイレへの誘導を一切やめてしまうのではなく、可能な限りはトイレでの排泄を促す努力も続けることが望ましいです。
おむつを上手に取り入れることで、愛犬との暮らしをより快適で穏やかなものにしていきましょう。
かかりつけの動物病院に相談する
老犬がトイレでしない問題に直面したとき、飼い主だけで悩みを抱え込まず、専門家である獣医師に相談することは非常に重要です。
特に、トイレの失敗が急に始まった場合や、他の体調変化を伴う場合は、何らかの病気が隠れている可能性が高いため、早期の受診が不可欠です。
動物病院に行くべきか迷ったときは、以下の点をチェックリストとして参考にしてください。
- トイレの失敗以外に、元気や食欲の低下が見られるか。
- 水を飲む量やおしっこの量が明らかに増えていないか(多飲多尿)。
- 尿の色が濃い、血が混じっている、キラキラしたものが混じるなど、見た目に異常はないか。
- 排尿時に痛がって鳴いたり、何度もいきんだりしていないか。
- 急に歩き方がおかしくなったり、段差を嫌がったりするようになったか。
- 昼夜逆転や夜鳴きなど、認知症を疑わせる行動はないか。
これらのうち、一つでも当てはまる項目があれば、なるべく早くかかりつけの動物病院で診察を受けましょう。
病気は早期発見・早期治療が何よりも大切です。
受診する際には、事前に情報を整理しておくと、診察がスムーズに進みます。
獣医師に伝えるべきポイントは以下の通りです。
的確な情報提供が重要
「いつからトイレの失敗が始まったか」「どのような場所で、どのくらいの頻度で失敗するのか」「尿や便の状態(色、量、硬さなど)」「他に気になる症状や行動の変化」などを具体的に伝えられるように、メモにまとめておくと良いでしょう。
可能であれば、粗相をした直後の尿をスポイトなどで採取して持参したり、失敗の様子を動画で撮影しておいたりすると、診断の大きな助けになります。
獣医師は、これらの情報と、身体検査、尿検査、血液検査、レントゲン検査などの結果を総合的に判断し、原因を特定します。
原因が病気であれば、その治療を行うことでトイレの問題も改善されます。
もし、特定の病気が見つからず、加齢によるものと診断された場合でも、獣医師は犬のQOL(生活の質)を向上させるための様々なアドバイスをしてくれます。
痛みを緩和するサプリメントの紹介や、認知症の進行を遅らせるための指導、介護に関する具体的なアドバイスなど、専門的な観点から飼い主をサポートしてくれます。
一人で抱え込まず、信頼できる動物病院をパートナーとして、愛犬の健康と快適な老後を支えていきましょう。
老犬がトイレでしない悩みと向き合いサポートしよう
この記事では、老犬がトイレでしない様々な原因と、具体的な対策について詳しく解説してきました。
愛犬のトイレの失敗は、飼い主にとって身体的にも精神的にも大きな負担となる、非常にデリケートな問題です。
毎日のように続く粗相の掃除に追われ、先の見えない介護に不安を感じ、時には愛犬に対して苛立ちを覚えてしまうこともあるかもしれません。
しかし、何よりも忘れてはならないのは、トイレの失敗は愛犬からの「助けを求めるサイン」だということです。
彼らは決して、あなたを困らせようとしているわけではありません。
体の自由が利かなくなったり、痛みを感じたり、不安な気持ちを抱えていたりと、犬自身が一番戸惑い、苦しんでいるのです。
だからこそ、飼い主である私たちが、そのサインを正しく受け止め、何が原因なのかを冷静に見極め、適切なサポートをしてあげることが求められます。
まずは、病気の可能性を疑い、動物病院で健康状態をチェックしてもらうこと。
そして、愛犬の身体の変化に合わせて、トイレの場所や広さ、床材など、生活環境を徹底的に見直してあげること。
決して叱らず、できた時には心から褒めてあげるという、愛情深いコミュニケーションを心がけること。
老犬の介護は、まさに若い頃のトイレトレーニングをもう一度やり直すような、根気と愛情のいる作業です。
時にはおむつのような介護グッズの力を借りることも、決して悪いことではありません。
大切なのは、飼い主自身が一人で抱え込みすぎず、心に余裕を持つことです。
利用できるものは上手に活用し、自分自身の休息も確保しながら、介護疲れに陥らないようにすることが、結果的に愛犬への優しいケアにつながります。
長年、家族としてたくさんの喜びと癒しを与えてくれた愛犬が、穏やかで尊厳のあるシニアライフを送れるように、最後の時まで愛情を持って寄り添ってあげましょう。
この記事が、老犬がトイレでしない問題に悩むすべての飼い主さんにとって、少しでも助けとなることを心から願っています。
本日のまとめ
- 老犬のトイレの失敗は加齢による自然な変化の一部
- 原因は筋力低下、認知症、病気、ストレスなど多岐にわたる
- 多飲多尿や血尿は病気のサインの可能性が高い
- 急なトイレの失敗はまず動物病院で健康診断を
- 関節の痛みが排泄姿勢を困難にしている場合がある
- トイレは寝床の近くなど複数箇所に設置するのが効果的
- トイレの範囲を広くし段差をなくす環境改善が重要
- 滑り止めマットを敷いて足腰の負担を軽減する
- 生活リズムを整え食後や起床後にトイレへ誘導する
- 粗相をしても絶対に叱らず冷静に後片付けをする
- 成功したら大いに褒めてポジティブな経験を積ませる
- 消臭スプレーで匂いを完全に消すことが再発防止の鍵
- おむつの活用は犬と飼い主双方のストレスを軽減する
- おむつ使用時は皮膚トラブル防止のため清潔を保つ
- 老犬がトイレでしない悩みは一人で抱えず専門家と協力しよう

愛犬の「食べない」に終止符を。手作り食レシピから生まれた『モグワン』
「せっかく買ったフードを食べてくれない…」そんな悩みを抱えていませんか?
『モグワン』は、愛犬の健康と食いつきの良さをとことん追求し、家庭での手作りごはんをヒントに誕生したプレミアムドッグフードです。
【モグワンが選ばれる3つの理由】
- 動物性タンパク源50%以上:新鮮なチキンとサーモンを贅沢に使用。封を開けた瞬間の香りが、愛犬の食欲を刺激します。
- 究極のグレインフリー:消化に負担をかける穀物を一切使わず、お腹にやさしいレシピを実現しました。
- ヒューマングレードの原材料:人間が食べる食材と同等の高品質な素材を厳選。着色料や香料も不使用で安心です。
毎日のごはんは、愛犬の体を作る大切な基盤。 「美味しそうに完食する姿が見たい」という飼い主さんの願いを、モグワンが叶えます。
今なら公式サイト限定の特別キャンペーンも実施中!まずは愛犬の驚くべき「食いつき」を体験してみませんか?
○○○○○○○○○○○○○○○○
子犬のトイレトレーニングはいつから?最適な時期と成功のコツ
成犬のトイレトレーニングのやり直し方|失敗原因と成功のコツ
○○○○○○○○○○○○○○○○
参考サイト
動物介護士が解説|老犬が外でしかトイレをしない!外から中へ変えてあげる方法 | TRIZA
老犬のトイレ失敗・しないときの原因と対策は?清潔に保つ工夫と介護のポイント
老犬のトイレ問題!解決のヒント | 【老犬ケア】老犬ホーム・老猫ホーム情報サイト
動物介護士が解説|老犬がトイレを失敗するようになったら要注意!対処法も | TRIZA
老犬はトイレの失敗が増える?飼い主ができるサポート例も

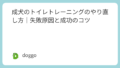
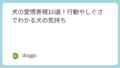
コメント