こんにちは、管理人のdoggoです
新しい家族として子犬を迎えることは、大きな喜びと興奮をもたらしてくれます。
しかし、その一方で、子犬を迎える準備には何から手をつければ良いのか、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、子犬を迎える準備を万全にするために必要なものから、具体的な費用、日々の生活における心構えまで、網羅的に解説していきます。
初めて犬を飼う方でも安心して新しい生活をスタートできるよう、お迎え当日の流れや、部屋の安全対策、さらにはトイレのしつけといった具体的なステップについても詳しく触れていきます。
また、子犬の健康を守るための動物病院選びや、新しい環境でのストレス対策など、見落としがちなポイントもしっかりとカバーします。
この記事を参考に、あなたと子犬の新しい生活が、幸せで満ち溢れたものになるよう、しっかりとした準備を進めていきましょう。
最終チェックリストも用意しているので、準備の総仕上げにぜひご活用ください。
◆このサイトでわかる事◆
- 子犬を迎えるために最低限必要なもののリスト
- お迎えにかかる初期費用と年間費用の目安
- 子犬が安全に暮らすための部屋の環境づくり
- 失敗しないトイレのしつけの基本的な方法
- 子犬の健康を考えたごはん選びの基準
- お迎え当日から始めるべきことと心構え
- 信頼できる動物病院を見つけるためのポイント

驚きの食いつき!愛犬が夢中になる『カナガン』で、真の健康を。
「最近ごはんの食べが悪い」「本当に安心できるものを与えたい」……そんな飼い主さんの悩みを解決するのが、世界中の愛犬家に選ばれている『カナガン』です。
【カナガンが支持される3つのこだわり】
- お肉・お魚が50%以上の高配合:新鮮なチキンやサーモンを贅沢に使用。良質なタンパク質が、愛犬の健康な筋肉と活力ある毎日をサポートします。
- 穀物不使用(グレインフリー):ワンちゃんが消化しにくいトウモロコシや小麦を一切排除。お腹にやさしく、アレルギーが気になる子にも安心です。
- 全年齢・全犬種対応の小粒サイズ:ドーナツ型の小さな粒は、子犬や小型犬でも噛み砕きやすく、サクサクとした食感で食欲をそそります。
「ごはんの時間が待ち遠しそう!」「毛並みのツヤが楽しみになった」と喜びの声も続々。 イギリスの厳しい基準をクリアした最高級の美味しさで、愛犬の瞳を輝かせてみませんか?
子犬を迎える準備で揃えるものリスト

◆この章のポイント◆
- まずは必要なものを揃えよう
- 迎える費用はどれくらい?
- 安心できる部屋の安全対策
- トイレのしつけは初日が肝心
- 子犬のごはん選びのポイント
まずは必要なものを揃えよう
子犬を迎える準備の第一歩は、新しい家族が快適に過ごせるよう、必要なものをリストアップして揃えることです。
お迎え当日に慌てないためにも、事前にリストを作成し、一つひとつ確認しながら準備を進めていくのが良いでしょう。
まず絶対に必要になるのが、子犬が安心して休める場所の確保です。
具体的には、サークルやケージ、そしてその中で使うベッドやマットが挙げられます。
サークルやケージは、子犬が自分だけのテリトリーとして認識できる空間となり、精神的な安定につながります。
また、留守番時や来客時など、安全を確保するためにも不可欠なアイテムと言えるでしょう。
次に食事関連のグッズです。
フードボウルとウォーターボウルは必須アイテムになります。
陶器製やステンレス製など、素材も様々ですが、子犬がひっくり返しにくく、清潔に保ちやすいものを選ぶことが大切です。
フードは、それまで子犬が食べていたものと同じ種類を用意するのが基本です。
急にフードを変えると、お腹を壊してしまう可能性があるからです。
トイレタリー用品も忘れてはいけません。
トイレトレーとペットシーツは、室内での排泄トレーニングに欠かせないものです。
トレーのサイズは、子犬が成長しても使えるように、少し大きめのものを選ぶと経済的かもしれません。
消臭スプレーやウェットティッシュなども併せて用意しておくと、粗相をした際にもすぐに対応できます。
お散歩デビューに向けて、首輪やハーネス、リードも準備しておきましょう。
ただし、子犬はすぐに大きくなるため、最初はサイズ調整がしやすいものを選ぶのがおすすめです。
その他にも、おもちゃやお手入れ用品(ブラシ、爪切り、シャンプーなど)、移動時に必要なキャリーバッグなど、揃えておきたいものはたくさんあります。
これらのアイテムをリストアップし、お迎えの1週間前までには全て揃えておくと安心です。
以下に、最低限必要なものを表としてまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
| カテゴリ | 必要なもの | 選ぶポイント |
|---|---|---|
| 居住スペース | サークル・ケージ、ベッド | 成長後も使えるサイズ、掃除のしやすさ |
| 食事関連 | フードボウル、ウォーターボウル、子犬用フード | 安定性のある素材、ブリーダーと同じフード |
| トイレ関連 | トイレトレー、ペットシーツ、消臭スプレー | 大きめのサイズ、吸収性の高いシーツ |
| お散歩グッズ | 首輪・ハーネス、リード | サイズ調整可能なもの、軽い素材 |
| お手入れ用品 | ブラシ、爪切り、シャンプー、歯ブラシ | 犬種に合ったもの、子犬用の低刺激なもの |
| その他 | おもちゃ、キャリーバッグ | 誤飲の危険がないサイズ、通気性の良いキャリー |
これらの準備をしっかりと行うことで、子犬は新しい環境にスムーズに慣れることができます。
そして、飼い主自身も落ち着いて子犬との新生活をスタートさせられるでしょう。
迎える費用はどれくらい?
子犬を迎える準備を進める上で、費用の計画は非常に重要な要素です。
一体どれくらいの費用がかかるのかを事前に把握しておくことで、経済的な不安なく新しい家族を迎えられます。
費用は大きく分けて「初期費用」と「年間費用」の2つに分類できます。
まず初期費用ですが、これは子犬をお迎えする際に一度だけかかる費用のことです。
最も大きな割合を占めるのが、子犬そのものの生体価格でしょう。
犬種や血統、購入する場所(ペットショップ、ブリーダーなど)によって価格は大きく異なりますが、数万円から数十万円、場合によってはそれ以上かかることもあります。
これに加えて、前述したケージや食器、トイレなどの飼育グッズ一式の購入費用がかかります。
一通り揃えると、安くても3万円から5万円程度は見込んでおくと良いかもしれません。
さらに、お迎えしてすぐに行うべき健康診断やワクチン接種、狂犬病予防注射の費用も初期費用に含まれます。
これらは合わせて2万円から3万円程度が目安です。
また、畜犬登録(約3,000円)も法律で義務付けられているため、忘れてはならない費用となります。
これらの初期費用を合計すると、生体価格にもよりますが、最低でも10万円から、一般的には20万円以上は見ておく必要があるでしょう。
次に年間費用です。
これは子犬を飼い始めてから継続的に発生する費用を指します。
主な内訳は以下の通りです。
- フード・おやつ代
- ペットシーツなどの消耗品費
- トリミング・シャンプー代(犬種による)
- フィラリア・ノミダニ予防薬代
- 年1回のワクチン・健康診断代
- ペット保険料(任意)
これらの費用は犬の大きさや犬種、ライフスタイルによって大きく変動しますが、小型犬の場合でも年間で15万円から30万円程度かかるのが一般的です。
特に、病気やケガをした際の医療費は高額になる可能性があるため、ペット保険への加入も検討しておくと安心かもしれません。
以下に費用の目安を表にまとめます。
| 費用の種類 | 項目 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 生体価格 | 5万円~50万円以上 | 犬種や購入先による |
| 飼育グッズ代 | 3万円~5万円 | ケージ、食器、トイレなど | |
| 医療費(初回) | 2万円~3万円 | ワクチン、健康診断など | |
| 畜犬登録料 | 約3,000円 | 市区町村への登録 | |
| 年間費用 | 食費 | 3万円~8万円 | フードのグレードや量による |
| 消耗品費 | 2万円~4万円 | ペットシーツ、ケア用品など | |
| 医療・予防費 | 3万円~5万円 | ワクチン、予防薬など | |
| トリミング代 | 0円~10万円 | 犬種や頻度による | |
| その他(保険など) | 3万円~6万円 | ペット保険料など |
子犬を迎えるということは、一つの命を預かるということです。
愛情はもちろんのこと、経済的な責任も伴うことを十分に理解し、無理のない飼育計画を立てることが何よりも大切です。
安心できる部屋の安全対策
子犬を迎える準備において、物理的なグッズを揃えるのと同じくらい重要なのが、家の中の環境を安全に整えることです。
好奇心旺盛な子犬は、人間が思いもよらないものを口にしたり、危険な場所に侵入したりすることがあります。
事故を未然に防ぎ、子犬が安心して過ごせる空間を作るための安全対策は必須と言えるでしょう。
まず最初に見直すべきは、電気コード類です。
子犬は動くものや細長いものに興味を示し、噛んでしまう習性があります。
電気コードを噛むと感電の危険があり、命に関わることもあります。
そのため、コード類は家具の裏に隠す、コードカバーで保護する、あるいは子犬の手が届かない高い位置に配置するなどの対策が必要です。
次に、誤飲の危険があるものを徹底的に片付けることです。
人間の薬、タバコ、小さなアクセサリー、ボタン、子供のおもちゃなどは、子犬にとって非常に危険です。
これらの物は、必ず蓋の閉まる容器に入れたり、引き出しの中にしまったりして、子犬の目に触れない、届かない場所に保管しましょう。
特に、玉ねぎやチョコレート、キシリトールガムなど、犬にとって中毒性のある食べ物は厳重に管理する必要があります。
キッチンやゴミ箱は子犬にとって魅力的な場所ですが、危険もたくさん潜んでいます。
キッチンにはベビーゲートなどを設置して侵入できないようにすると安心です。
ゴミ箱は、蓋付きのものを選び、簡単に倒されないように工夫しましょう。
観葉植物の中にも、犬にとって有毒なものが存在します。
ポインセチアやユリ、アイビーなどはその代表例です。
もし室内に置いている場合は、子犬がアクセスできない場所に移動させるか、手放すことを検討してください。
また、床の滑り対策も重要になります。
フローリングの床は滑りやすく、子犬が走った際に股関節などを痛める原因となることがあります。
カーペットやペット用のマットを敷くことで、足腰への負担を軽減し、ケガを予防できます。
家具の角にコーナーガードを取り付けたり、倒れやすい背の高い家具を固定したりといった対策も有効です。
これらの安全対策は、一度行ったら終わりではありません。
子犬の成長に合わせて行動範囲は広がり、届く場所も高くなっていきます。
定期的に部屋の中を見渡し、危険な箇所がないかをチェックする習慣をつけることが、愛犬の安全を守る上で非常に大切なのです。
安心して子犬との生活をスタートさせるために、お迎え前に家族全員で家の中を点検しましょう。
トイレのしつけは初日が肝心
子犬を迎える準備の中で、多くの飼い主が最も気になることの一つがトイレのしつけではないでしょうか。
トイレトレーニングは根気が必要ですが、正しい方法で初日から取り組むことで、その後のしつけが格段に楽になります。
成功の鍵は、子犬の習性を理解し、失敗を叱るのではなく、成功を褒めることにあります。
まず、子犬を家に迎えたら、一番最初にトイレの場所に連れて行ってあげましょう。
サークルやケージの中にトイレトレーを設置し、そこが排泄をする場所であることを優しく教えます。
子犬は環境の変化で緊張しているかもしれませんが、地面の匂いをクンクンと嗅がせ、少し様子を見てください。
もしそこで排泄できたら、大げさなくらいに褒めてあげることが重要です。
「すごいね!」「えらいね!」と高い声で褒め、おやつを少し与えるのも効果的でしょう。
これにより、子犬は「ここで排泄すると良いことがある」と学習していきます。
子犬が排泄をしたくなるタイミングを把握することも、トイレトレーニングを成功させるための重要なポイントです。
一般的に、子犬は以下のようなタイミングでトイレに行きたくなります。
- 朝起きたとき
- ごはんを食べた後
- 水を飲んだ後
- 遊んだ後や興奮した後
- 寝て起きた後
これらのタイミングを見計らって、子犬をトイレの場所に誘導してあげましょう。
また、床の匂いを嗅ぎながらソワソワし始めたり、クルクルと回り始めたりするのも、排泄のサインです。
このサインを見逃さずにトイレへ連れて行くことで、成功体験を積ませることができます。
もし、トイレ以外の場所で粗相をしてしまっても、絶対に大声で叱ったり、鼻を押し付けたりしてはいけません。
子犬はなぜ叱られているのかを理解できず、排泄行為そのものが悪いことだと勘違いしてしまいます。
その結果、飼い主の見ていない場所で隠れて排泄するようになってしまう可能性があります。
粗相を見つけた場合は、何も言わずに静かに片付けるのが鉄則です。
その際、消臭スプレーを使って匂いを完全に取り除くことが大切です。
匂いが残っていると、そこをトイレの場所だと認識してしまい、同じ場所で繰り返してしまうからです。
トイレのしつけは、一朝一夕に完璧になるものではありません。
特に、家に迎えたばかりの頃は失敗が続いて当たり前です。
焦らず、根気強く、そして何よりも愛情を持って向き合うことが成功への一番の近道となります。
成功をたくさん褒めて、子犬に自信をつけさせてあげましょう。
子犬のごはん選びのポイント
子犬の健やかな成長にとって、毎日のごはんは非常に重要な役割を果たします。
子犬を迎える準備として、どのようなフードを選べば良いのかを事前に学んでおくことは、飼い主の責任の一つです。
市場には様々な種類のドッグフードが溢れているため、何を基準に選べば良いのか迷ってしまうかもしれません。
しかし、いくつかのポイントを押さえることで、愛犬に最適なごはんを選ぶことができます。
まず最も大切なことは、「総合栄養食」と記載されているフードを選ぶことです。
総合栄養食とは、そのフードと水だけで、犬が必要とする栄養素をバランス良く摂取できるように作られているフードのことを指します。
子犬期は、骨格や筋肉、内臓などが急速に発達するとても大切な時期です。
この時期に栄養バランスの取れた食事を与えることが、将来の健康の礎となります。
次に、子犬のライフステージに合ったフードを選びましょう。
ドッグフードは、「子犬用(パピー用)」「成犬用(アダルト用)」「高齢犬用(シニア用)」など、年齢に合わせて栄養成分が調整されています。
子犬用のフードは、成犬用に比べて高タンパク・高カロリーに設計されており、成長期に必要な栄養素が豊富に含まれています。
必ず「子犬用」または「全年齢対応」と表示されているものを選んでください。
フードの主原料もチェックしたいポイントの一つです。
原材料表示は、含まれている量が多いものから順番に記載されています。
最初にチキンやラム、サーモンなどの良質な動物性タンパク質が記載されているフードは、犬の食性に合っていると言えるでしょう。
一方で、トウモロコシや小麦などの穀物が主原料となっているフードは、犬によっては消化不良やアレルギーの原因となる可能性も指摘されています。
フードの種類には、ドライフード、ウェットフード、セミモイストフードなどがあります。
それぞれにメリット・デメリットがありますが、一般的には栄養バランスが良く、保存性にも優れ、歯の健康維持にも役立つドライフードが主流です。
お迎えしたばかりの頃は、ブリーダーやペットショップで与えられていたフードと同じものを与え、環境に慣れてきたら、徐々に新しいフードに切り替えていくのが良いでしょう。
フードを切り替える際は、1週間から10日ほどかけて、今までのフードに新しいフードを少しずつ混ぜながら割合を増やしていくようにします。
急な切り替えは、下痢や嘔吐の原因となることがあるため注意が必要です。
愛犬の食いつきや便の状態をよく観察しながら、その子に合った最適なフードを見つけてあげることが大切です。
もしフード選びに迷ったら、獣医師やペットショップの専門スタッフに相談してみるのも良い方法です。
子犬を迎える準備における心構えと注意点
◆この章のポイント◆
- お迎え当日の過ごし方
- 早めに動物病院を見つけよう
- ストレス対策も忘れずに
- 家族としての心構えを大切に
- 最終チェックリストで確認
- 完璧な子犬を迎える準備で楽しい毎日を
お迎え当日の過ごし方
子犬を迎える準備がすべて整い、いよいよお迎え当日を迎えたときの過ごし方は、その後の子犬との関係構築において非常に重要です。
飼い主にとっては待ちに待った嬉しい日ですが、子犬にとっては親兄弟から引き離され、知らない場所、知らない人々に囲まれる、不安とストレスでいっぱいの一日であることを忘れてはいけません。
当日は、子犬の気持ちに寄り添い、できるだけ静かで落ち着いた環境を提供してあげることが何よりも大切です。
まず、お迎えの移動手段ですが、必ずキャリーバッグを用意しましょう。
車で移動する場合は、キャリーを座席にしっかりと固定し、急ブレーキや急ハンドルを避けて安全運転を心がけます。
公共交通機関を利用する場合も、他の乗客の迷惑にならないよう配慮が必要です。
移動中は、子犬が不安にならないように、時々優しく声をかけてあげると良いでしょう。
家に到着したら、まずは事前に用意しておいたサークルやケージに子犬を入れてあげます。
そして、一番最初にトイレの場所を教えてあげることが肝心です。
その後は、子犬が自分から出てくるまで、そっと見守ってあげましょう。
嬉しさのあまり、家族みんなで代わる代わる抱っこしたり、撫で回したりしたくなる気持ちは分かりますが、それは子犬にとって大きな負担となります。
最初の数日間は、過度なスキンシップは避け、子犬が自ら環境に慣れていくのを見守る姿勢が大切です。
食事は、ブリーダーやペットショップで聞いておいた時間と量を目安に与えます。
環境の変化で食欲が落ちることもありますが、元気な様子であれば少し様子を見ても大丈夫です。
水はいつでも新鮮なものが飲めるように、ウォーターボウルに用意しておきましょう。
夜鳴きをすることがあるかもしれません。
これは、寂しさや不安からくる行動です。
ここで可哀想だからとケージから出してしまうと、「鳴けば構ってもらえる」と学習してしまいます。
心を鬼にして、声をかけずに無視するのが基本的な対応となります。
ケージを布で覆って暗くしてあげたり、飼い主の匂いがついたタオルを入れてあげたりすると、安心して眠れることもあります。
お迎え当日は、親戚や友人を招くのは絶対に避けるべきです。
家族以外の人間との接触は、子犬にとってさらなるストレスの原因となります。
まずは家族だけで、静かに、穏やかに、新しい家族の一員を迎えてあげましょう。
この日の過ごし方が、子犬が新しい家を「安心できる場所」だと認識するための第一歩となるのです。
早めに動物病院を見つけよう
子犬を迎える準備の一環として、お迎えする前にかかりつけとなる動物病院を見つけておくことは、非常に重要なことです。
元気そうに見える子犬でも、環境の変化によるストレスや、もともと持っていた病気が原因で、突然体調を崩してしまうことがあります。
そんな万が一の事態に備えて、いざという時にすぐに相談できる獣医師の存在は、飼い主にとって大きな心の支えとなるでしょう。
動物病院を選ぶ際には、いくつかのポイントがあります。
まず第一に、自宅からのアクセスが良いことです。
緊急時にすぐに連れて行ける距離であることはもちろん、ワクチン接種や定期的な健康診断で通うことを考えると、通院のしやすさは大切な要素です。
駐車場があるかどうかも、車で移動する場合には確認しておきたいポイントになります。
次に、病院の診療時間や休診日、そして夜間や休診日の救急対応についても調べておきましょう。
かかりつけの病院が時間外に対応していない場合でも、提携している夜間救急病院などを紹介してもらえるか確認しておくと、より安心です。
病院の雰囲気や、獣医師、動物看護師などのスタッフとの相性も重要です。
実際に病院を訪れてみて、待合室や診察室が清潔に保たれているか、スタッフの対応が丁寧で親切かなどを自分の目で確かめてみることをお勧めします。
飼い主の些細な質問にも丁寧に答えてくれ、納得のいく説明をしてくれる獣医師は信頼できます。
また、その獣医師が得意とする分野や、病院が導入している医療設備(レントゲン、エコー、血液検査機器など)についても、ホームページなどで確認しておくと良いでしょう。
特定の犬種がかかりやすい病気について詳しいなど、専門性も判断材料の一つとなります。
近所の犬を飼っている人からの口コミや評判も、非常に参考になる情報源です。
散歩中などに他の飼い主さんと話す機会があれば、どこの動物病院に通っているか、その病院の評判はどうかなどを聞いてみるのも良い方法かもしれません。
子犬をお迎えしたら、特に問題がなくても、まずは一度健康診断に連れて行くことを推奨します。
これにより、子犬の健康状態を初期段階で把握できるだけでなく、病院の雰囲気に慣れさせておくことができます。
「病院は怖い場所ではない」と子犬に思ってもらうことが、今後のスムーズな通院につながるのです。
愛犬の生涯にわたる健康をサポートしてくれる、信頼できるパートナーとして、最適な動物病院をじっくりと選びましょう。
ストレス対策も忘れずに
子犬にとって、新しい家に来ることは大きな環境の変化であり、想像以上のストレスがかかっています。
母犬や兄弟犬と離れ、見知らぬ場所で、知らない人々と暮らすことになるのですから、不安や恐怖を感じるのは当然のことです。
子犬を迎える準備では、このような子犬のストレスをいかに軽減してあげるかを考えることも、飼い主の重要な役割となります。
まず、お迎えしてから数日間は、子犬に静かな環境を提供し、ゆっくりと休ませてあげることが最優先です。
前述の通り、過度なスキンシップや、大きな物音は避けるべきです。
サークルやケージを、家族が頻繁に通らないリビングの隅などに設置し、子犬が一人で落ち着ける「安全地帯」を確保してあげましょう。
ケージに布をかけて、外からの刺激を遮断してあげるのも効果的です。
子犬が新しい環境に慣れるまでは、長時間の留守番はさせないように配慮が必要です。
可能であれば、家族の誰かが数日間はそばにいられるように、迎える時期を調整するのが理想的でしょう。
どうしても留守番が必要な場合は、短時間から始め、徐々に時間を延ばしていくようにします。
適度な運動や遊びは、ストレス発散に役立ちます。
しかし、ワクチンプログラムが終了するまでは、他の犬との接触や、不特定多数の犬が利用する場所へのお散歩は控えなければなりません。
それまでは、室内で安全なおもちゃを使って、短い時間遊んであげるのが良いでしょう。
飼い主との遊びは、信頼関係を築く上でも大切なコミュニケーションの時間となります。
遊びすぎは子犬を興奮させすぎ、かえってストレスになることもあるため、時間を決めて切り上げることが大切です。
子犬の様子をよく観察することも、ストレスのサインを見逃さないために重要です。
- 下痢や軟便が続く
- 食欲がない
- 震えが止まらない
- 体を過剰に舐めたり噛んだりする
- ずっと隠れて出てこない
上記のような行動が見られる場合は、ストレスを感じている可能性があります。
環境を見直したり、静かに過ごさせる時間を増やしたりといった対応が必要です。
症状が続くようであれば、動物病院に相談しましょう。
新しい生活リズムに慣れるまでには、個体差はありますが、数週間から1ヶ月程度かかることもあります。
飼い主は焦らず、子犬のペースに合わせて、ゆっくりと関係を築いていくという大らかな気持ちを持つことが、何よりのストレス対策になるのです。
家族としての心構えを大切に
子犬を迎える準備として、物や環境を整えることはもちろん大切ですが、それ以上に重要なのが、飼い主となる家族全員の「心構え」を一つにしておくことです。
犬を飼うということは、これから10数年にわたり、一つの命に責任を持つということです。
その犬の一生が幸せなものになるかどうかは、飼い主の心構えと行動にかかっています。
まず、家族全員が子犬を迎えることに賛成していることが大前提となります。
誰か一人でも乗り気でなかったり、アレルギーの問題があったりする場合、後々大きなトラブルに発展しかねません。
お迎えする前に、必ず家族全員で話し合い、全員が納得した上で決断することが不可欠です。
次に、しつけや世話に関するルールを家族間で統一しておくことが重要になります。
例えば、「人間の食べ物は絶対に与えない」「ソファの上には乗せない」「コマンド(おすわり、まてなど)は特定の言葉を使う」といったルールです。
人によって言うことが違ったり、態度が異なったりすると、子犬は混乱してしまい、しつけがうまく進まない原因となります。
お父さんは叱るけど、お母さんは許してくれる、といった状況は絶対に避けなければなりません。
誰が主にお世話をするのか、役割分担を決めておくことも大切です。
朝晩の散歩は誰が行くのか、ごはんをあげるのは誰か、トイレの掃除は誰が担当するのか、など、具体的な役割を決めておくことで、特定の人に負担が偏るのを防ぐことができます。
もちろん、状況に応じて協力し合う姿勢が基本ですが、メインの担当者を決めておくとスムーズです。
子犬は、可愛いだけの存在ではありません。
吠えたり、いたずらをしたり、病気になったりすることもあります。
トイレの失敗も、最初のうちは頻繁に起こるでしょう。
そんな時に、感情的に叱りつけるのではなく、なぜそのような行動をするのかを理解しようと努め、根気強く向き合う覚悟が必要です。
犬の習性や行動学について、本やインターネットで事前に学んでおくことも、心構えを育む上で非常に役立ちます。
そして何よりも、子犬を「ペット」としてではなく、「家族の一員」として生涯愛し続けるという覚悟を持つことが最も大切です。
楽しい時も、大変な時も、常に寄り添い、共に時間を過ごしていく。
そのような強い意志と愛情が、飼い主としての心構えの根幹をなすのです。
家族全員でこの心構えを共有できて初めて、子犬を迎える準備が本当に整ったと言えるでしょう。
最終チェックリストで確認
これまでに解説してきた子犬を迎える準備について、いよいよ最終確認の段階です。
お迎えの日が近づいてきたら、抜け漏れがないかをリストを使って一つひとつチェックしていくと安心です。
頭の中だけで確認していると、意外なことを見落としてしまう可能性があります。
ここでは、これまでの内容を総まとめにした最終チェックリストを用意しました。
物理的な「モノの準備」と、知識や心構えといった「コトの準備」の2つの側面から確認していきましょう。
このリストを印刷したり、スマートフォンにメモしたりして、家族みんなで確認作業を行うことをお勧めします。
モノの準備チェックリスト
以下のアイテムがすべて揃っているか、そして正しく設置されているかを確認しましょう。
| チェック項目 | 確認済み | 備考 |
|---|---|---|
| サークル・ケージは設置したか | ☐ | 落ち着ける場所に設置 |
| ベッドやマットは用意したか | ☐ | ケージ内に設置 |
| フードボウル・ウォーターボウルはあるか | ☐ | 安定感のあるもの |
| 子犬用のフードは用意したか | ☐ | ブリーダーと同じものが理想 |
| トイレトレーとペットシーツは準備したか | ☐ | ケージ内またはすぐそばに設置 |
| 首輪(ハーネス)とリードはあるか | ☐ | サイズ調整可能なもの |
| キャリーバッグは用意したか | ☐ | お迎えの移動時に必須 |
| お手入れ用品(ブラシ、爪切り等)は揃っているか | ☐ | 犬種に合ったもの |
| 誤飲の危険があるものは片付けたか | ☐ | 子犬の目線で部屋をチェック |
| 電気コードの保護は完了したか | ☐ | カバーを付ける、家具の裏に隠す |
| 滑りやすい床の対策はしたか | ☐ | マットやカーペットを敷く |
| 有毒な観葉植物は室内にないか | ☐ | 撤去または届かない場所へ移動 |
コトの準備チェックリスト
次に、家族の知識や意識が共有できているかを確認します。
| チェック項目 | 確認済み | 備考 |
|---|---|---|
| かかりつけの動物病院は決まっているか | ☐ | 連絡先と場所を控えておく |
| 家族全員が犬を迎えることに賛成しているか | ☐ | アレルギーの有無も確認 |
| しつけの方針やルールは家族で統一したか | ☐ | コマンドや禁止事項など |
| お世話の役割分担は話し合ったか | ☐ | 散歩、ごはん、掃除など |
| お迎え当日の過ごし方を確認したか | ☐ | 静かに見守るのが基本 |
| トイレトレーニングの基本を理解したか | ☐ | 叱らず褒める |
| 子犬にストレスを与えない配慮を学んだか | ☐ | 過度なスキンシップは避ける |
| 生涯飼育の覚悟はできているか | ☐ | 経済的、時間的責任を含む |
これらのリストがすべてチェックで埋まったなら、あなたは子犬を迎える準備が万全であると言えるでしょう。
もちろん、実際に飼い始めてから気づくことや、新たに必要なものが出てくることもあります。
しかし、このリストにある基本的な準備ができていれば、大きな問題なく新しい生活をスタートできるはずです。
自信を持って、新しい家族を迎え入れてください。
完璧な子犬を迎える準備で楽しい毎日を
ここまで、子犬を迎える準備について、必要なもののリストアップから始まり、費用計画、部屋の安全対策、しつけの基本、そして家族としての心構えに至るまで、多岐にわたる項目を詳しく解説してきました。
新しい家族を迎える前の期間は、期待に胸を膨らませると同時に、多くの不安や疑問がつきまとうものです。
しかし、一つひとつのステップを丁寧に進め、万全の準備を整えることで、その不安は自信へと変わっていくでしょう。
子犬との生活は、私たちに計り知れないほどの喜びと癒やしを与えてくれます。
純粋な瞳で見つめられたり、全身で喜びを表現してくれたりする姿は、日々の疲れを忘れさせ、心を豊かにしてくれます。
一方で、生き物を育てるということは、大きな責任を伴うことも事実です。
毎日の散歩や食事の世話、しつけ、そして時には病気やケガの看病も必要になります。
楽しいことばかりではなく、大変なこと、悩むこともたくさんあるでしょう。
だからこそ、事前の準備が何よりも重要になるのです。
今回ご紹介した内容を参考に、物理的な環境を整えることはもちろん、犬という動物の習性を学び、家族全員で意識を共有し、愛情を持って接していく覚悟を固めてください。
そのしっかりとした土台があれば、これから起こるであろう様々な出来事にも、きっと冷静に、そして前向きに対処していくことができるはずです。
完璧な子犬を迎える準備とは、高価なグッズを揃えることではありません。
子犬の安全と健康を第一に考え、その一生に責任を持つという心構えを家族全員で持つこと、これに尽きると言えるでしょう。
あなたの準備が、これから始まる子犬との素晴らしい日々の礎となることを心から願っています。
本日のまとめ
- 子犬を迎える準備はモノとコトの両面から行う
- 必要なものリストで飼育グッズを揃える
- 初期費用と年間費用を把握し計画を立てる
- 部屋の安全対策は子犬の目線で徹底的に
- 電気コードの保護と誤飲防止は最優先事項
- トイレのしつけは初日から褒めて教える
- ごはんは子犬用の総合栄養食を選ぶ
- お迎え当日は静かな環境で休ませる
- かかりつけの動物病院を事前に見つけておく
- 環境の変化による子犬のストレスに配慮する
- 家族全員が犬を迎えることに賛成し協力する
- しつけのルールは家族内で必ず統一する
- 生涯にわたり命を預かる心構えを持つ
- 最終チェックリストで準備の抜け漏れを防ぐ
- 万全な準備が子犬との幸せな生活の第一歩

驚きの食いつき!愛犬が夢中になる『カナガン』で、真の健康を。
「最近ごはんの食べが悪い」「本当に安心できるものを与えたい」……そんな飼い主さんの悩みを解決するのが、世界中の愛犬家に選ばれている『カナガン』です。
【カナガンが支持される3つのこだわり】
- お肉・お魚が50%以上の高配合:新鮮なチキンやサーモンを贅沢に使用。良質なタンパク質が、愛犬の健康な筋肉と活力ある毎日をサポートします。
- 穀物不使用(グレインフリー):ワンちゃんが消化しにくいトウモロコシや小麦を一切排除。お腹にやさしく、アレルギーが気になる子にも安心です。
- 全年齢・全犬種対応の小粒サイズ:ドーナツ型の小さな粒は、子犬や小型犬でも噛み砕きやすく、サクサクとした食感で食欲をそそります。
「ごはんの時間が待ち遠しそう!」「毛並みのツヤが楽しみになった」と喜びの声も続々。 イギリスの厳しい基準をクリアした最高級の美味しさで、愛犬の瞳を輝かせてみませんか?
○○○○○○○○○○○○○○○○
犬の散歩はいつから?最適な時期とデビュー前の準備を解説
犬の健康寿命を延ばす秘訣とは?食事や運動、飼い主の愛情
○○○○○○○○○○○○○○○○
参考サイト
初めて子犬を迎える準備ガイド!犬の飼育に必要なものとは – Breeder Families
子犬を迎え入れるのに必要な準備 | Royal Canin JP
子犬を迎える準備|初めて犬を飼う際に必要なものややっておくことを解説! – 愛犬ブリーダー
子犬を迎えるまでにやっておくこと 揃えておくものチェックリスト – みんなのブリーダー
はじめて子犬を迎える際の準備は?飼い方、心構えなどについても解説 – Petio
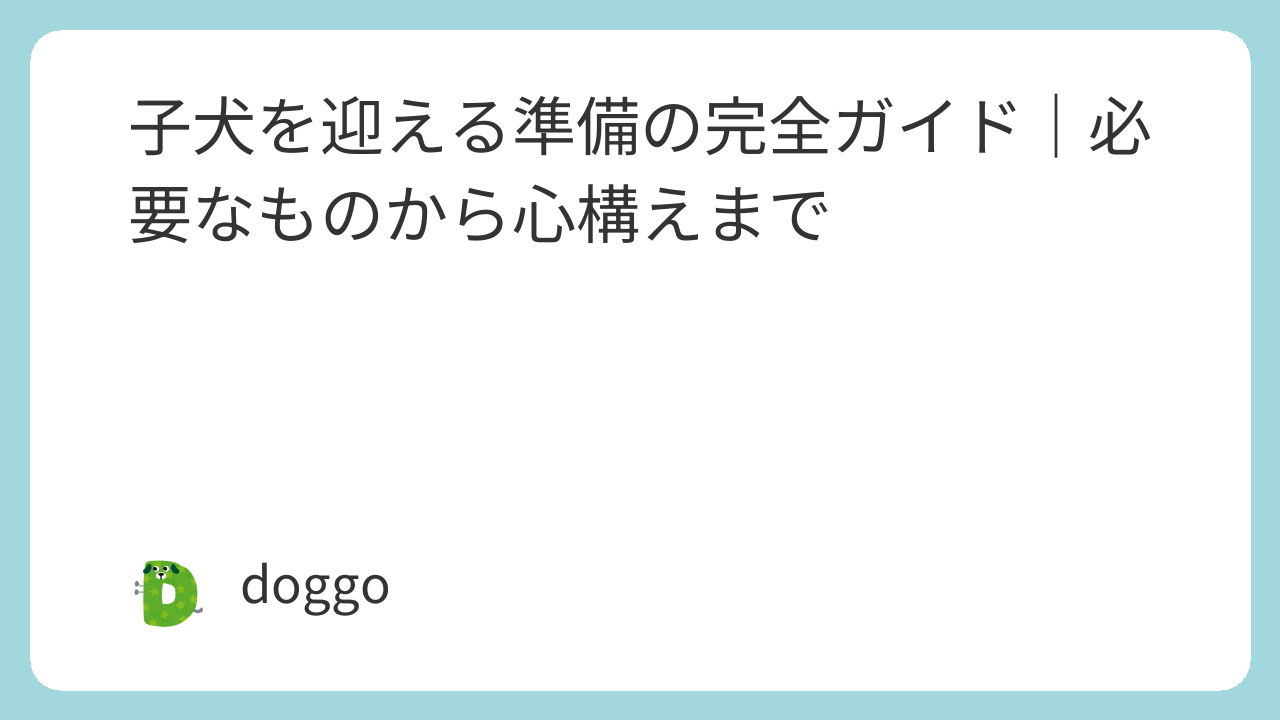
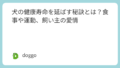
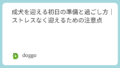
コメント