こんにちは、管理人のdoggoです
「うちの子、最近寝てばかりいるけれど大丈夫かな…」「もしかして、睡眠時間が足りていないのかもしれない」。
愛犬との暮らしの中で、その睡眠時間について気になったことはありませんか。
あまりに長く寝ていると病気を心配してしまいますし、逆に短いとストレスを感じていないか不安になるものです。
犬の睡眠時間は、人間とは大きく異なり、そのライフステージや犬種、個々の性格によっても大きく変わってきます。
子犬や老犬(シニア犬)であれば睡眠が長くなる傾向がありますし、成犬であっても1日の半分以上を寝て過ごすことは決して珍しいことではありません。
大切なのは、平均的な時間を知ること以上に、ご自身の愛犬にとっての健康的な睡眠サイクルを理解し、その変化に気づいてあげることです。
この記事では、犬は何時間寝るのがベストという疑問に、年齢別の目安を示しながらお答えします。
さらに、睡眠時間が長い場合や短い場合に考えられる原因、そして愛犬が心からリラックスできる睡眠環境の作り方まで、具体的な方法を交えて詳しく解説していきます。
この記事を読み終える頃には、愛犬の睡眠に関する不安が解消され、今日から実践できる快眠のためのヒントをきっと見つけていただけるでしょう。
◆このサイトでわかる事◆
- 犬の年齢別の適切な睡眠時間
- 子犬や老犬の睡眠時間が長くなる理由
- 犬の眠りが浅い「レム睡眠」の役割
- 睡眠時間が長い場合に注意すべき病気のサイン
- 睡眠時間が短い原因となるストレス要因
- 愛犬が安心して熟睡できる環境作りのポイント
- 睡眠の質を高めるための生活習慣の見直し方

愛犬の「食べない」に終止符を。手作り食レシピから生まれた『モグワン』
「せっかく買ったフードを食べてくれない…」そんな悩みを抱えていませんか?
『モグワン』は、愛犬の健康と食いつきの良さをとことん追求し、家庭での手作りごはんをヒントに誕生したプレミアムドッグフードです。
【モグワンが選ばれる3つの理由】
- 動物性タンパク源50%以上:新鮮なチキンとサーモンを贅沢に使用。封を開けた瞬間の香りが、愛犬の食欲を刺激します。
- 究極のグレインフリー:消化に負担をかける穀物を一切使わず、お腹にやさしいレシピを実現しました。
- ヒューマングレードの原材料:人間が食べる食材と同等の高品質な素材を厳選。着色料や香料も不使用で安心です。
毎日のごはんは、愛犬の体を作る大切な基盤。 「美味しそうに完食する姿が見たい」という飼い主さんの願いを、モグワンが叶えます。
今なら公式サイト限定の特別キャンペーンも実施中!まずは愛犬の驚くべき「食いつき」を体験してみませんか?
犬は何時間寝るのがベストかライフステージ別に解説
犬の睡眠時間は、人間のように夜にまとめて眠るスタイルとは大きく異なります。
彼らは一日のうちに短い睡眠を何度も繰り返す「多相性睡眠」というパターンをとるのが特徴です。
そのため、合計すると人間よりもずっと長い時間を睡眠に費やしています。
しかし、その最適な睡眠時間は、犬の成長段階、つまりライフステージによって大きく変動するものです。
ここでは、子犬、成犬、そして老犬(シニア犬)という3つのステージに分けて、それぞれ犬は何時間寝るのがベストなのか、その目安と理由を詳しく見ていきましょう。
また、犬種や個体差、さらには犬特有の睡眠サイクルについても解説し、愛犬の睡眠をより深く理解するための一助とします。
◆この章のポイント◆
- 子犬期は1日18時間以上の睡眠が必要
- 成犬の平均睡眠時間は12〜15時間
- 老犬(シニア犬)は体力の衰えで長く寝る
- 犬種や個体差によっても睡眠時間は異なる
- 犬の眠りが浅い理由と睡眠サイクル
子犬期は1日18時間以上の睡眠が必要
生まれたばかりの子犬は、私たちの想像をはるかに超える時間を睡眠に費やします。
一般的に、生後数ヶ月の子犬は1日のうち18時間から20時間、時にはそれ以上眠ることも珍しくありません。
まるで「寝るのが仕事」であるかのように、食べて、少し遊んではすぐに眠ってしまう姿に、驚く飼い主さんも多いのではないでしょうか。
しかし、これほど長い睡眠時間は、子犬が健やかに成長するために不可欠な生理現象なのです。
子犬が長時間眠る主な理由は、その急速な身体の成長にあります。
睡眠中、特に深い眠りの間に「成長ホルモン」が最も活発に分泌されます。
このホルモンは、骨や筋肉、内臓など、体を作るあらゆる組織の発達を促す重要な役割を担っています。
つまり、子犬は眠ることで文字通り体を大きくしているわけです。
また、脳の発達にとっても睡眠は極めて重要と考えられます。
日中に経験した様々な出来事、例えば飼い主との触れ合いや新しいおもちゃの匂い、外の音といった情報を、睡眠中に整理し、記憶として定着させています。
これは社会性を身につけ、学習能力を高めるための大切なプロセスと言えるでしょう。
さらに、子犬は成犬に比べて体力がなく、非常に疲れやすいです。
起きている間は見るもの聞くものすべてが新鮮で、好奇心旺盛に活動するため、エネルギーの消費も激しくなります。
そのため、こまめに睡眠をとって体力を回復させ、次の活動に備える必要があるのです。
この時期の睡眠を妨げることは、健全な発育を阻害する可能性もあります。
子犬が眠っている時は、無理に起こしたりせず、静かに見守ってあげることが大切です。
安心して休めるように、静かで快適な寝床を用意してあげることも忘れないようにしましょう。
子犬の長い睡眠時間は、心と体の両方が健康に成長している証拠なのです。
成犬の平均睡眠時間は12〜15時間
子犬期を卒業し、心身ともに成熟した成犬になると、睡眠時間は少し落ち着いてきます。
一般的に、成犬の平均的な睡眠時間は1日に12時間から15時間程度とされています。
それでも1日の半分以上を寝て過ごしている計算になり、人間の平均睡眠時間(7〜8時間)と比べるとかなり長いことがわかります。
なぜ成犬はこれほど長く眠るのでしょうか。
その理由の一つは、犬がもともと狩りをして暮らしていた頃の習性に由来します。
野生の犬科動物は、狩りのために瞬発的なエネルギーを必要とします。
獲物を見つけた時に素早く行動できるよう、それ以外の時間はできるだけ体を休め、エネルギーを温存しておく必要がありました。
その名残が、ペットとして暮らす現代の犬にも受け継がれていると考えられています。
また、成犬の睡眠は、ただ体を休めるためだけのものではありません。
日中の活動で疲労した筋肉を修復したり、免疫機能を維持したりと、健康を保つための重要なメンテナンス時間でもあります。
特に、活発に運動した日や、ドッグランなどで他の犬とたくさん交流した日などは、心身の疲れを癒やすためにより多くの睡眠を必要とすることもあるでしょう。
ただし、この「12〜15時間」という数字はあくまで平均的な目安です。
飼い主のライフスタイルも、犬の睡眠時間に大きく影響します。
例えば、飼い主が日中仕事で留守にしている家庭では、犬は特にすることがなく、退屈しのぎにうたた寝をして過ごす時間が長くなる傾向があります。
一方で、飼い主が在宅で常に活動している環境であれば、犬もそれに合わせて起きている時間が長くなるかもしれません。
重要なのは、愛犬が毎日安定した睡眠時間を確保できているかどうかです。
日中に十分な休息がとれていれば、夜も落ち着いて眠ることができるでしょう。
愛犬の普段の様子をよく観察し、睡眠が足りているか、あるいは長すぎないかを見極めてあげることが大切になります。
老犬(シニア犬)は体力の衰えで長く寝る
犬も人間と同じように、年齢を重ねるにつれて心身に様々な変化が現れます。
7歳から8歳頃(犬種によって異なります)を過ぎ、シニア期に入った老犬に見られる最も顕著な変化の一つが、睡眠時間の増加です。
若い頃よりも明らかに寝ている時間が長くなり、1日に18時間以上眠ることも決して珍しくありません。
まるで子犬時代に戻ったかのように見えるその姿に、飼い主さんは少し寂しさを感じたり、体調を心配したりするかもしれません。
老犬の睡眠時間が長くなる最大の理由は、基礎体力の低下です。
加齢とともに筋肉量が減少し、心肺機能も若い頃より衰えてくるため、少し動いただけでも疲れやすくなります。
以前は平気だった散歩の距離でも、シニア期になると大きな負担になることがあります。
そのため、活動によって消費したエネルギーを回復させるため、より長い休息、つまり睡眠が必要になるのです。
また、感覚器官の衰えも睡眠時間に影響を与えることがあります。
視力や聴力が低下してくると、周囲の状況を把握するために今まで以上に神経を使うようになり、精神的な疲労が溜まりやすくなります。
その結果、脳を休ませるために睡眠時間が長くなる傾向が見られます。
さらに、関節炎などの痛みを伴う病気を抱えている場合、体を動かすことが億劫になり、自然と横になっている時間が増えることもあります。
ただし、老犬の睡眠時間が長くなるのは、ある程度は自然な老化現象です。
しかし、「ただの老化だから」と安易に判断するのは危険な場合もあります。
もし、睡眠時間が急激に増えた、呼びかけへの反応が極端に鈍くなった、食欲や元気がないといった他の症状が見られる場合は、何らかの病気が隠れている可能性も否定できません。
甲状腺機能低下症や心臓病、認知症などが原因で活動性が低下し、寝てばかりいるように見えることもあります。
愛犬がシニア期に入ったら、睡眠時間の変化だけでなく、日中の様子や食欲、排泄の状態なども含めて、総合的に健康状態をチェックする習慣をつけることが、病気の早期発見につながります。
犬種や個体差によっても睡眠時間は異なる
これまでライフステージ別の睡眠時間について解説してきましたが、「犬は何時間寝るのがベスト」という問いに対する答えは、すべての犬に共通する単一のものではありません。
なぜなら、犬の睡眠時間は犬種が持つ特性や、一頭一頭の個性によっても大きく左右されるからです。
まず、犬種による違いについて見てみましょう。
一般的に、大型犬は小型犬に比べて睡眠時間が長い傾向があると言われています。
例えば、グレート・デーンやセント・バーナードのような超大型犬は、その大きな体を維持するために多くのエネルギーを必要とし、体を休めるためにより多くの睡眠を要することがあります。
一方で、ボーダー・コリーやジャック・ラッセル・テリアといった牧羊犬や猟犬として活躍してきた犬種は、もともと活動的に働くように作られているため、比較的短い睡眠時間でも平気な場合があります。
ただし、これもあくまで一般的な傾向に過ぎません。
次に、個体差の影響も非常に大きいと言えます。
人間にもショートスリーパーやロングスリーパーがいるように、犬にもそれぞれ持って生まれた体質があります。
同じ犬種、同じ年齢の兄弟犬であっても、片方はのんびり屋で寝るのが好き、もう一方は活発で常に何かしていたい、といった性格の違いが見られます。
好奇心旺盛で遊び好きな性格の犬は、起きている時間が長くなるかもしれませんし、逆に穏やかで落ち着いた性格の犬は、うたた寝をしながら静かに過ごすことを好むでしょう。
また、その日の活動量も睡眠時間に直接影響します。
普段より長い距離を散歩した日や、新しい場所へ出かけて多くの刺激を受けた日などは、心身ともに疲れて睡眠時間が長くなるのが普通です。
このように、愛犬の睡眠時間を評価する際には、平均的なデータと比べるだけでなく、その子の犬種、性格、そして日々の生活スタイルを考慮に入れることが不可欠です。
大切なのは、「他の犬と比べて長いか短いか」ではなく、「普段のその子と比べて変化はないか」という視点を持つことです。
愛犬の「いつも通り」を把握しておくことが、健康管理の第一歩となります。
犬の眠りが浅い理由と睡眠サイクル
愛犬が寝ている様子を観察していると、小さな物音ですぐに目を覚ましたり、耳をピクピクと動かしたりしていることに気づくでしょう。
このことからも分かるように、犬の睡眠は全体的に浅いという特徴があります。
この「眠りの浅さ」は、犬の祖先が野生で生きていた頃の習性と深く関係しています。
犬の睡眠は、人間と同じように「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という2つのステージを繰り返しています。
ノンレム睡眠は、脳も体も休んでいる深い眠りの状態です。
一方、レム睡眠は、体は休んでいますが脳は活動している浅い眠りの状態を指します。
人間の場合、このレム睡眠が全睡眠時間に占める割合は約25%ですが、犬の場合は約80%がレム睡眠だと言われています。
つまり、犬は睡眠時間の大半を、いつでもすぐに起き上がれる浅い眠りの状態で過ごしているのです。
これは、野生環境で生き抜くための重要な生存戦略でした。
外敵からの攻撃にいち早く気づき、すぐさま逃げるか反撃に移るためには、ぐっすり熟睡しているわけにはいきません。
常に周囲の気配を察知できるよう、眠りは浅く、短く、そして断続的である必要があったのです。
この名残から、ペットとして安全な環境で暮らす現代の犬たちも、睡眠のほとんどをレム睡眠の状態で過ごしています。
寝ている時に、脚をパタパタさせたり、鼻をクンクン鳴らしたり、しっぽを振ったりするのは、夢を見ている証拠であり、脳が活発に動いているレム睡眠中によく見られる行動です。
眠りが浅いために、犬は不足しがちな睡眠の質を量で補う必要があります。
これが、犬の合計睡眠時間が人間よりも長くなる大きな理由の一つです。
短い睡眠を何度も繰り返すことで、トータルとして必要な休息を確保しています。
飼い主としては、愛犬が安心して深い眠り(ノンレム睡眠)に入れる時間を少しでも作ってあげることが大切です。
犬が熟睡している時は、邪魔をしないように静かにしてあげましょう。
特に、家族が集まるリビングなどで寝ている場合は、テレビの音量や生活音に少し配慮するだけでも、愛犬の睡眠の質は向上するはずです。
愛犬にとって犬は何時間寝るのがベストか見極める方法
愛犬の健康を願う飼い主にとって、「うちの子の睡眠時間は本当にこれで大丈夫だろうか」という心配は尽きないものです。
ライフステージや犬種による平均的な睡眠時間を知ることは一つの目安になりますが、最終的に大切なのは、目の前にいる愛犬の個性に合わせた判断です。
ここでは、平均値だけにとらわれず、愛犬にとって本当に犬は何時間寝るのがベストなのかを見極めるための具体的な方法を探っていきます。
睡眠時間が普段より長い場合や、逆に短い場合に、どのようなサインに注意すべきか。
そして、愛犬が毎日質の高い睡眠をとれるように、飼い主として何ができるのか。
安心できる環境作りから、日々の生活習慣の重要性、さらには睡眠の質を高めるための工夫まで、多角的な視点から解説します。
◆この章のポイント◆
- 睡眠時間が長すぎる場合に潜む病気のサイン
- 睡眠時間が短い場合に考えられるストレス
- 愛犬が安心できる睡眠環境の作り方
- 散歩や食事など生活習慣の重要性
- 飼い主ができる睡眠の質を高める工夫
- 愛犬にとって犬は何時間寝るのがベストか見つけよう
睡眠時間が長すぎる場合に潜む病気のサイン
「最近、愛犬が以前よりずっと長く寝ている気がする」。
老犬であれば老化現象の一つかもしれませんが、成犬や、まだ若い犬の睡眠時間が急激に増えた場合は、何らかの体調不良のサインである可能性を疑う必要があります。
単に疲れているだけ、あるいは退屈なだけということもありますが、中には病気が原因で活動性が低下し、結果として寝ている時間が長くなっているケースも少なくありません。
ここでは、過剰な睡眠の裏に隠れているかもしれない病気のサインについて解説します。
まず、注意すべきは睡眠時間以外の変化です。
ただ長く寝ているだけでなく、同時に以下のような症状が見られないか注意深く観察してください。
- 食欲がない、または極端に増えた
- 水を飲む量や尿の量が異常に多い
- 元気がない、散歩に行きたがらない
- 歩き方がおかしい、足を引きずる
- 呼吸が速い、咳をする
- 体重が急に増えたり減ったりした
これらの症状が伴う場合、次のような病気の可能性が考えられます。
甲状腺機能低下症
体の新陳代謝をコントロールする甲状腺ホルモンの分泌が減少する病気です。
代謝が落ちるため、元気がなくなり、寒がりになり、寝てばかりいるようになります。
食欲がないのに体重が増える、皮膚が乾燥して毛が抜けるといった症状も特徴的です。
心臓病
心臓の機能が低下すると、全身に十分な血液を送り出すことができなくなります。
そのため、少し動くだけで息切れしてしまい、疲れやすくなるため、活動を避けて寝ている時間が増えます。
特に、咳(特に夜間や興奮時)が見られる場合は注意が必要です。
関節炎などの痛み
関節に痛みがあると、動くのが億劫になり、じっと寝ていることが多くなります。
立ち上がったり座ったりする動作をためらう、階段を嫌がる、散歩中に座り込むといった行動が見られたら、どこかに痛みを感じているサインかもしれません。
糖尿病
血糖値のコントロールがうまくできなくなる病気です。
多飲多尿、食欲旺盛なのに痩せていくといった症状のほか、体がだるくなるため元気がなくなり、寝てばかりいることがあります。
認知症(高齢犬の場合)
昼夜が逆転し、夜中に徘徊して昼間はぐったりと寝ていることが多くなります。
他にも、名前を呼んでも反応が薄い、狭い場所に入り込んで動けなくなるなどの行動変化が見られます。
愛犬の睡眠時間が気になった時は、日々の様子を記録しておくと、動物病院で診察を受ける際に非常に役立ちます。
少しでも「おかしいな」と感じたら、自己判断せずに獣医師に相談することが、愛犬の健康を守るために最も重要です。
睡眠時間が短い場合に考えられるストレス
犬の睡眠時間が長すぎることへの心配がある一方で、「うちの子はあまり眠らないけれど大丈夫だろうか」と、睡眠時間の短さに不安を感じる飼い主さんもいます。
犬の睡眠は浅く断続的であるため、飼い主が認識している以上に休息をとっていることも多いですが、それでも明らかに落ち着きがなく、熟睡できている様子がない場合は、何らかのストレスを抱えているサインかもしれません。
犬は言葉で不満や不安を伝えられないため、行動の変化でそのサインを示すことがあります。
睡眠不足や不眠は、その代表的なサインの一つです。
犬がストレスを感じ、睡眠時間が短くなる原因としては、身体的なものと精神的なものの両方が考えられます。
身体的な原因
体のどこかに痛みやかゆみがあると、気になってしまい熟睡できません。
例えば、皮膚炎によるかゆみ、関節炎の痛み、あるいは消化器系の不快感(腹痛や吐き気)などです。
また、シニア犬の場合は、夜間の頻尿や、認知症による不安感から夜中に何度も起きてしまうこともあります。
呼吸器系の疾患(短頭種気道症候群など)があると、呼吸が苦しくて眠りが浅くなることも考えられます。
精神的な原因
精神的なストレスも、犬の睡眠に大きな影響を与えます。
特に、環境の変化は犬にとって大きなストレス要因となり得ます。
- 引っ越し
- 家族構成の変化(新しいペット、赤ちゃんの誕生など)
- 飼い主のライフスタイルの変化(転職、在宅勤務の終了など)
- 長時間の留守番による分離不安
これらの変化は、犬にとって安心できる環境が揺らぐことを意味し、不安からリラックスできなくなり、眠りが浅くなってしまうのです。
また、運動不足もストレスの原因となります。
犬は日中に適度な運動をすることでエネルギーを発散し、心身ともに満たされます。
散歩が足りていなかったり、室内での遊びが不足していたりすると、有り余ったエネルギーが発散できず、夜になっても興奮状態が続いて眠れなくなることがあります。
さらに、雷や花火の大きな音、近所の工事の騒音なども、犬にとっては恐怖の対象となり、安心して眠れない原因になります。
もし愛犬の睡眠時間が短いと感じたら、まずはその原因を探ってあげることが大切です。
体に不調はなさそうか、生活環境に変化はなかったか、日中の活動量は十分か、などを振り返ってみましょう。
原因に心当たりがあれば、それを取り除いてあげることで、愛犬は再び安心して眠れるようになるはずです。
愛犬が安心できる睡眠環境の作り方
犬が質の高い睡眠をとるためには、心からリラックスできる「安心安全な寝床」が不可欠です。
野生時代の犬は、外敵から身を守れる巣穴のような場所を寝床にしていました。
その習性は今も残っており、現代の犬も、静かで、少し狭く、周りを見渡せるような場所を好む傾向があります。
愛犬に最高の睡眠をプレゼントするために、どのような環境を整えてあげればよいのでしょうか。
ここでは、理想的な睡眠環境を作るための具体的なポイントをいくつかご紹介します。
寝床の場所選び
犬の寝床を設置する場所は非常に重要です。
まず、人の出入りが激しい玄関や廊下、テレビのすぐそばなど、騒がしい場所は避けましょう。
物音や光の刺激で、眠りの浅い犬はすぐに目を覚ましてしまいます。
おすすめなのは、リビングの隅など、家族の気配を感じられるけれど、直接的な邪魔が入らない静かな場所です。
犬は群れで暮らす動物なので、完全に孤立した部屋よりも、飼い主の存在を感じられる方が安心して眠れることが多いです。
また、エアコンの風が直接当たる場所や、窓際の温度変化が激しい場所も避けるべきです。
ベッドやクレートの活用
寝床には、愛犬の体に合ったサイズのベッドを用意してあげましょう。
フカフカで体を包み込むようなドーナツ型のベッドや、あごを乗せやすい縁のあるタイプなどが人気です。
季節に合わせて、夏は涼しい素材、冬は暖かい素材のものに変えてあげると、より快適に過ごせます。
さらに効果的なのが、クレートやハウスを寝床として活用することです。
四方が囲まれたクレートは、犬にとってまさに巣穴のような空間であり、非常に安心感を覚えます。
普段から「クレートは安心できる自分の部屋」だと教えておくと、来客時や災害時などにも役立ちます。
中に飼い主の匂いがついたタオルなどを入れてあげると、さらにリラックス効果が高まるでしょう。
温度と湿度の管理
快適な睡眠のためには、室内の温度と湿度の管理も欠かせません。
犬は人間よりも体温調節が苦手で、特に暑さには弱いです。
夏場はエアコンを活用し、室温を25〜26度程度に保つのが理想です。
冬場も、寒すぎると体に負担がかかるため、暖房器具で適度な温度を維持しましょう。
その際、犬が自分で涼しい場所や暖かい場所に移動できるよう、部屋の中に温度差のある場所を作っておくと、自分で快適な場所を選べます。
愛犬がいつも同じ場所でなく、フローリングで寝たりベッドで寝たりしているのは、自分で体温調節をしている証拠かもしれません。
これらのポイントを参考に、愛犬だけの特別なリラックス空間を作ってあげてください。
散歩や食事など生活習慣の重要性
犬の睡眠の質は、寝床の環境だけでなく、日中の過ごし方、つまり生活習慣に大きく左右されます。
人間が「日中にしっかり活動し、夜にバランスの取れた食事をとるとよく眠れる」のと同じように、犬にも心身の健康を保ち、質の高い睡眠へと導くための適切な生活リズムがあります。
ここでは、特に重要となる「散歩(運動)」と「食事」の2つの観点から、生活習慣が睡眠に与える影響について解説します。
散歩と運動の役割
犬にとって散歩は、単なるトイレの時間ではありません。
散歩は、肉体的なエネルギーを発散させるだけでなく、外の匂いを嗅いだり、他の犬や人と会ったりすることで、精神的な刺激を受け、欲求を満たすための非常に重要な活動です。
日中に適度な運動を行うことで、体は心地よい疲労感を覚え、夜の深い眠りにつながります。
運動が不足すると、有り余ったエネルギーが原因で夜になっても興奮状態が続き、なかなか寝付けない、あるいは眠りが浅くなることがあります。
逆に、過度な運動は体を興奮させすぎてしまい、かえって睡眠を妨げることもあるため注意が必要です。
犬種や年齢に合った適切な量と質の運動を、毎日決まった時間に行うことが、体内時計を整え、健康的な睡眠サイクルを確立する鍵となります。
朝晩2回の散歩を基本とし、週末にはドッグランで思い切り走らせるなど、メリハリのある運動を取り入れるのも良いでしょう。
食事の時間と内容
食事もまた、犬の睡眠リズムに深く関わっています。
食事の時間は、できるだけ毎日同じ時間に設定することが望ましいです。
規則正しい食事時間は、犬の体内時計を正常に保ち、消化器系の働きを安定させます。
特に注意したいのが、寝る直前の食事です。
就寝前に食事をとると、睡眠中も消化器官が活発に働き続けなければならず、体が完全にリラックスできません。
その結果、眠りが浅くなったり、夜中に便意や尿意で目覚めてしまったりする原因になります。
夕食は、就寝時間の数時間前には済ませておくのが理想的です。
また、食事の内容も重要です。
栄養バランスの取れた総合栄養食を基本とし、愛犬の年齢や活動量に合ったフードを選びましょう。
消化に悪い食べ物や、アレルギーの原因となる食材は、体の不快感を引き起こし、安眠を妨げる可能性があります。
このように、毎日の散歩や食事が規則正しく行われることで、犬の生活に予測可能なリズムが生まれます。
この安定したリズムこそが、犬に安心感を与え、心穏やかな睡眠へと誘うための土台となるのです。
飼い主ができる睡眠の質を高める工夫
愛犬の睡眠環境や生活習慣を整えることに加えて、飼い主の日々のちょっとした工夫や関わり方が、愛犬の睡眠の質をさらに高めることにつながります。
犬は飼い主の感情や行動に非常に敏感な動物です。
飼い主がリラックスして穏やかに接することが、犬の安心感となり、結果として質の高い睡眠をもたらします。
ここでは、今日からすぐに実践できる、愛犬の安眠をサポートするための工夫をいくつかご紹介します。
就寝前のリラックスタイム
人間と同じように、犬も眠りにつく前には、興奮状態から心身をクールダウンさせる時間が必要です。
夜寝る前には、ボール投げや引っ張りっこといった激しい遊びは避けましょう。
代わりに、優しく体を撫でてあげたり、穏やかな声で話しかけたりするスキンシップの時間を設けるのがおすすめです。
ブラッシングも、犬にとっては心地よいマッサージとなり、リラックス効果が期待できます。
このような静かな時間を過ごすことで、犬は「もうすぐ寝る時間だ」と認識し、自然と眠りの準備に入ることができます。
部屋の照明を少し暗くしたり、静かな音楽をかけたりするのも良い方法です。
トイレは寝る前に済ませる
夜中にトイレで起きてしまうと、睡眠が中断され、その質が低下してしまいます。
特に子犬や老犬はトイレが近くなりがちなので、就寝前には必ずトイレに連れて行き、排泄を済ませておく習慣をつけましょう。
これにより、朝までぐっすり眠れる可能性が高まります。
寝る直前の過度な水分摂取は控えるようにすることも、夜中のトイレを防ぐ上で効果的です。
飼い主自身の生活リズムを整える
犬は飼い主の生活リズムに大きく影響されます。
飼い主の就寝時間や起床時間がバラバラだと、犬の体内時計も乱れがちになり、安定した睡眠サイクルを築くのが難しくなります。
可能な限り、毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きるように心がけましょう。
飼い主が規則正しい生活を送ることが、結果的に愛犬の生活リズムを整え、健康的な睡眠をサポートすることに繋がるのです。
もし飼い主が夜更かしをしていると、犬も「まだ活動時間だ」と勘違いしてしまい、なかなか寝付いてくれないかもしれません。
これらの工夫は、特別な道具や多くの時間を必要とするものではありません。
大切なのは、愛犬の気持ちに寄り添い、安心して休めるようなサインを送ってあげることです。
日々の暮らしの中に少しだけ取り入れて、愛犬との絆を深めながら、最高の睡眠をサポートしてあげましょう。
愛犬にとって犬は何時間寝るのがベストか見つけよう
ここまで、犬の睡眠について様々な角度から解説してきました。
ライフステージによる睡眠時間の違い、睡眠時間に影響を与える要因、そして睡眠の質を高めるための具体的な方法など、多くの情報に触れてきました。
最終的に、この記事を通して最も伝えたいメッセージは、「犬は何時間寝るのがベスト」という問いに対する絶対的な正解はない、ということです。
12時間や15時間といった数字は、あくまで一般的な目安に過ぎません。
本当に大切なのは、平均値と比べることではなく、あなたの愛犬を日々観察し、その子にとっての「普通」や「快適」を見つけてあげることです。
愛犬の普段の睡眠時間を把握し、その上で、寝起きの様子や日中の活動レベルをチェックしてみましょう。
ぐっすり眠った後に元気に起き、楽しそうに遊び、美味しそうにご飯を食べるのであれば、たとえ睡眠時間が平均より少し長くても短くても、その子にとってはそれがベストな睡眠時間なのかもしれません。
逆に、睡眠時間に大きな変化があったり、元気や食欲がないといった他のサインが見られたりした場合には、注意が必要です。
それは、愛犬が送る何らかのSOSのサインである可能性があります。
その小さな変化にいち早く気づき、適切に対応してあげることこそ、飼い主の最も重要な役割と言えるでしょう。
今回ご紹介した、睡眠環境の整え方や生活習慣の見直しは、すべての犬の健康と幸せに繋がる基本的なケアです。
愛犬が毎日安心して、心穏やかに眠れるようにサポートしてあげることは、愛犬の寿命を延ばし、共に過ごす時間をより豊かなものにしてくれるはずです。
これからも愛犬の様子を愛情深く見守り続け、その子だけの「犬は何時間寝るのがベスト」の答えを、ぜひ見つけてあげてください。
本日のまとめ
- 犬の睡眠時間はライフステージで大きく異なる
- 子犬は成長のために1日18時間以上眠る
- 成犬の平均睡眠時間は12時間から15時間
- 老犬は体力低下により睡眠時間が長くなる傾向
- 犬の睡眠の大半はすぐに起きれる浅いレム睡眠
- 睡眠時間が急に増えた場合は病気の可能性を疑う
- 食欲不振や元気消失が伴う場合は特に注意が必要
- 睡眠不足はストレスや身体の不調が原因かも
- 環境の変化は犬にとって大きなストレスになる
- 安心して眠れる静かで快適な寝床を用意する
- クレートの活用は犬に安心感を与えるのに効果的
- 毎日の散歩と規則正しい食事が睡眠リズムを整える
- 就寝前のリラックスタイムが質の高い眠りを誘う
- 飼い主の規則正しい生活が犬の体内時計を安定させる
- 大切なのは平均との比較より愛犬個体の観察

愛犬の「食べない」に終止符を。手作り食レシピから生まれた『モグワン』
「せっかく買ったフードを食べてくれない…」そんな悩みを抱えていませんか?
『モグワン』は、愛犬の健康と食いつきの良さをとことん追求し、家庭での手作りごはんをヒントに誕生したプレミアムドッグフードです。
【モグワンが選ばれる3つの理由】
- 動物性タンパク源50%以上:新鮮なチキンとサーモンを贅沢に使用。封を開けた瞬間の香りが、愛犬の食欲を刺激します。
- 究極のグレインフリー:消化に負担をかける穀物を一切使わず、お腹にやさしいレシピを実現しました。
- ヒューマングレードの原材料:人間が食べる食材と同等の高品質な素材を厳選。着色料や香料も不使用で安心です。
毎日のごはんは、愛犬の体を作る大切な基盤。 「美味しそうに完食する姿が見たい」という飼い主さんの願いを、モグワンが叶えます。
今なら公式サイト限定の特別キャンペーンも実施中!まずは愛犬の驚くべき「食いつき」を体験してみませんか?
参考サイト
犬の睡眠時間の目安とは?愛犬が快眠できる環境づくり – ペット保険ステーション
犬は1日どのくらい寝るの?睡眠時間と快適に眠れる環境づくりのポイント – PLUS CYCLE
愛犬が寝てばかりだけど、大丈夫?犬の睡眠時間について解説 – ペットライン
チワワに必要な睡眠時間について|よく寝るのは大丈夫?ライフステージごとの違いも解説!
【獣医師監修】犬の睡眠時間はどれくらい?短くて大丈夫?獣医師が解説します | GREEN DOG & CAT
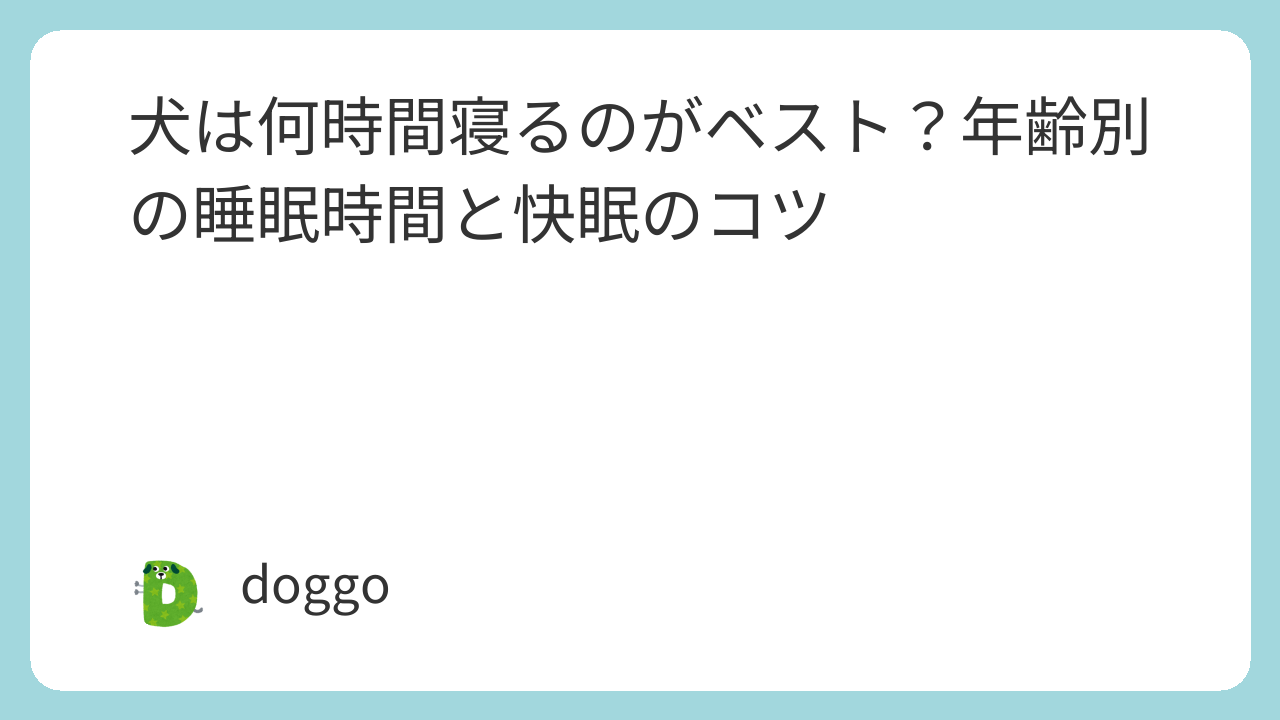
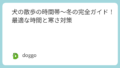
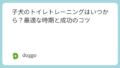
コメント