こんにちは、管理人のdoggoです
愛犬の様子がいつもと違う、なんだか元気がない、でもご飯はしっかり食べる…。
そんな状況に、飼い主さんとしては「病気なのかな?」「でも食欲はあるし…」と、どう判断すれば良いか分からず不安な気持ちになりますよね。
犬が元気ないけどご飯は食べるという状態は、一時的なものから、実は病気が隠れているサインまで、さまざまな原因が考えられます。
特に、嘔吐や下痢、震えといった他の症状が見られる場合や、高齢犬である場合は注意が必要です。
また、散歩に行きたがらない、寝てばかりいるといった行動の変化も重要な手がかりとなります。
この記事では、犬が元気ないけどご飯は食べる時に考えられる原因、ストレスとの関係、考えられる病気、そして飼い主さんが取るべき対処法について、具体的なチェックポイントを交えながら詳しく解説していきます。
すぐに動物病院へ行くべきか、それとも少し様子を見るべきか、その判断基準を明確にし、愛犬の健康を守るためのお手伝いをします。
◆このサイトでわかる事◆
- 犬が元気ないけどご飯は食べる時に考えられる原因
- ストレスが原因で見られる症状と見分け方
- 嘔吐や下痢、震えなど注意すべき他の症状
- 高齢犬の場合に特有の原因とケア方法
- 自宅で様子を見るか病院へ行くかの判断基準
- 動物病院を受診する際に伝えるべき情報
- 飼い主ができる家庭での具体的な対処法

愛犬の「食べない」に終止符を。手作り食レシピから生まれた『モグワン』
「せっかく買ったフードを食べてくれない…」そんな悩みを抱えていませんか?
『モグワン』は、愛犬の健康と食いつきの良さをとことん追求し、家庭での手作りごはんをヒントに誕生したプレミアムドッグフードです。
【モグワンが選ばれる3つの理由】
- 動物性タンパク源50%以上:新鮮なチキンとサーモンを贅沢に使用。封を開けた瞬間の香りが、愛犬の食欲を刺激します。
- 究極のグレインフリー:消化に負担をかける穀物を一切使わず、お腹にやさしいレシピを実現しました。
- ヒューマングレードの原材料:人間が食べる食材と同等の高品質な素材を厳選。着色料や香料も不使用で安心です。
毎日のごはんは、愛犬の体を作る大切な基盤。 「美味しそうに完食する姿が見たい」という飼い主さんの願いを、モグワンが叶えます。
今なら公式サイト限定の特別キャンペーンも実施中!まずは愛犬の驚くべき「食いつき」を体験してみませんか?
犬が元気ないけどご飯は食べるのは病気のサイン?
◆この章のポイント◆
- 考えられる原因はストレスや環境の変化
- 嘔吐や下痢など他の症状もチェック
- 高齢犬にみられる元気消失の理由
- こんな震えは危険な病気の可能性も
- まずは慌てずに様子を見ること
考えられる原因はストレスや環境の変化
犬が元気ないけどご飯は食べる場合、まず考えられるのが精神的なストレスや生活環境の変化です。
犬は非常に繊細な動物であり、人間が気付かないような些細な変化も敏感に感じ取ります。
食欲は本能的な欲求であるため、多少のストレスでは失われにくいことがありますが、活動意欲は精神状態に大きく左右されるのです。
例えば、引っ越しや部屋の模様替え、新しい家具の導入などは、犬にとって大きな環境の変化となります。
慣れ親しんだ匂いやテリトリーの感覚が変わることで、不安を感じて元気がなくなってしまうことがあります。
また、家族構成の変化も大きな要因です。
新しい家族が増えたり、逆によく遊んでくれた人が家を出て行ったりすると、犬は混乱や寂しさを感じます。
特に、赤ちゃんが生まれた家庭では、飼い主さんの関心が赤ちゃんに向きがちになるため、犬がやきもちを焼いて元気をなくすケースは少なくありません。
さらに、飼い主さんの生活リズムの変化も影響を与えます。
仕事が忙しくなって散歩の時間が短くなったり、遊んであげる時間が減ったりすると、犬は愛情不足や退屈を感じてストレスを溜め込みます。
来客が多い、近所で工事が始まったなど、騒音や見知らぬ人との接触が続くことも、犬にとっては大きなストレス源です。
これらのストレスが原因の場合、犬は不安から特定の人や場所に隠れる、飼い主の後をついて回る、体を過剰に舐めるといった行動を見せることもあります。
食欲が落ちていないからと安心せず、最近の生活に何か変化がなかったかを注意深く振り返ることが、原因を特定する第一歩となるでしょう。
ストレスが原因であれば、原因を取り除くか、安心できる環境を整えてあげることで、徐々に元気を取り戻すことが期待できます。
嘔吐や下痢など他の症状もチェック
犬が元気ないけどご飯は食べるという状況で、最も注意すべきなのは、他にどのような症状が出ているかという点です。
食欲があるからといって、全ての病気の可能性が否定されるわけではありません。
特に消化器系の異常は、初期段階では食欲が維持されることもあります。
まず確認したいのが、嘔吐や下痢の有無です。
一度きりの嘔吐で、その後はケロッとしているなら、早食いや空腹が原因の生理的なものである可能性もあります。
しかし、何度も繰り返し吐く、吐瀉物に血や異物が混じっている、吐こうとしても何も出ないといった様子が見られる場合は、胃腸炎や異物の誤飲、さらには胃捻転のような緊急性の高い病気も疑われます。
下痢についても同様で、一時的な軟便であれば食事内容の変更などが原因かもしれませんが、水のような下痢が続く、血便や黒色便が出る、しぶるような様子を見せるなどの場合は、感染症や内臓疾患のサインかもしれません。
次に、呼吸の状態も重要なチェックポイントです。
安静にしているにもかかわらず、呼吸が速い、浅い、あるいは苦しそうにしている場合は、心臓や肺に問題がある可能性が考えられます。
咳やくしゃみ、鼻水といった症状も、呼吸器系の感染症やアレルギーの兆候です。
その他にも、体を頻繁にかく、皮膚に赤みや発疹がある、特定の場所を痛がる(触ると鳴く、かばうように歩く)、おしっこの色や量、回数がいつもと違うなど、全身の状態をくまなく観察することが大切です。
これらの追加の症状は、病気を特定するための非常に重要な手がかりとなります。
元気がないという主観的な情報に加えて、嘔吐や下痢の回数、色、状態などを具体的に記録しておくと、動物病院を受診した際に、より正確な診断の助けとなります。
食欲があるからと軽視せず、他の小さなサインを見逃さないようにしましょう。
高齢犬にみられる元気消失の理由
高齢犬(シニア犬)が元気ないけどご飯は食べる場合、加齢に伴う様々な体の変化が原因となっていることが多く、若い犬とは少し異なる視点での観察が必要です。
年齢を重ねることで、犬も人間と同じように身体機能が徐々に低下していきます。
最も一般的な原因の一つが、関節の痛みです。
変形性関節症などは多くの高齢犬に見られ、歩いたり立ったりする際に痛みを感じるため、自然と動くことを避けるようになります。
飼い主さんからは、ただ寝てばかりいて元気がないように見えますが、食欲は変わらないため、病気だと気付きにくいことがあります。
散歩に行きたがらない、階段の上り下りを嫌がる、立ち上がるのに時間がかかるといったサインが見られたら、関節の痛みを疑ってみるべきでしょう。
また、心臓や腎臓といった内臓機能の低下も、元気消失の原因となります。
特に慢性腎臓病などは、初期段階では食欲が落ちないまま、なんとなく元気がない、水をたくさん飲むといった症状から始まることが多い病気です。
心臓病の場合も、疲れやすくなるため活動量が減り、元気がないように見えます。
さらに、視力や聴力の低下も、犬の行動に影響を与えます。
周りの状況が把握しにくくなることで不安を感じ、あまり動かなくなったり、飼い主さんの呼びかけへの反応が鈍くなったりします。
これが元気がないように見える原因となることもあります。
認知機能不全症候群、いわゆる犬の認知症も考えられます。
昼夜逆転して夜鳴きをする、狭い場所に入り込んで動けなくなる、ぐるぐると同じ場所を回り続けるといった特徴的な行動のほかに、単にぼーっとしている時間が増え、活動性が低下することもあります。
高齢犬の場合、「年のせい」と片付けてしまいがちですが、その元気のなさが病気のサインであることも少なくありません。
食欲があるからと安心せず、定期的な健康診断を受け、日々の小さな変化に気を配り、愛犬が快適なシニアライフを送れるようにサポートしてあげることが重要です。
こんな震えは危険な病気の可能性も
犬が元気ないけどご飯は食べるという状態に加えて、「震え」が見られる場合は、特に注意深い観察が必要です。
犬の震えには、寒さや恐怖、興奮といった生理的な原因から、病気を原因とするものまで様々な背景があります。
まず、生理的な震えとの見分けが重要です。
寒い日にブルブルと震えるのは体温を上げようとする自然な反応です。
また、雷や花火の音に怯えている時や、飼い主さんの帰宅に興奮している時に震えることもあります。
これらの震えは、原因がはっきりしており、その状況が解消されれば収まるのが特徴です。
一方で、特に原因が見当たらないのに震えている、体を丸めてじっとしながら震えているといった場合は、体のどこかに痛みを感じているサインかもしれません。
椎間板ヘルニアや関節炎、腹痛など、犬は痛みを隠そうとする習性があるため、震えが唯一のSOSであることもあります。
特定の部位を触ろうとすると嫌がる、抱き上げようとすると鳴くといった反応があれば、痛みが原因である可能性はさらに高まります。
また、神経系の異常が震えを引き起こしている可能性も考えられます。
てんかんの発作の部分的な症状として震えが見られたり、脳腫瘍や脳炎などの病気が原因で全身または体の一部が痙攣したりすることもあります。
この場合、意識が朦朧としたり、よだれを大量に垂らしたりといった他の神経症状を伴うこともあります。
さらに、中毒も震えの原因となり得ます。
チョコレートや玉ねぎ、殺虫剤、不凍液などを誤って口にしてしまった場合、神経症状の一つとして震えや痙攣が現れることがあります。
低血糖や腎不全による尿毒症など、代謝性の問題でも震えは起こり得ます。
元気がない状態に加えて、痛みを伴うような震えや、意識レベルの低下を伴う震えが見られる場合は、緊急性が高い可能性があります。
どのような状況で、体のどの部分が、どのくらいの時間震えているのかをよく観察し、動画に撮っておくと、診察の際に役立ちます。
安易に判断せず、速やかに動物病院を受診することを強くお勧めします。
まずは慌てずに様子を見ること
愛犬に元気がない様子が見られると、飼い主としてはすぐに心配になり、慌ててしまうものです。
しかし、犬が元気ないけどご飯は食べるという状況で、他に嘔吐や下痢、震えといった深刻な症状が見られない場合は、まずは落ち着いて愛犬の様子を注意深く観察することが大切です。
一時的な疲れや、ちょっとしたストレスが原因で、半日〜1日程度元気がなくなることは、犬にもよくあることです。
例えば、前日にドッグランで思い切り走り回った、長時間のドライブをした、ペットホテルに預けられたなど、心当たりがある場合は、単なる疲労が原因かもしれません。
このような場合は、静かで安心できる環境でゆっくりと休ませてあげることが最善の対処法です。
無理に構ったり、散歩に連れ出そうとしたりせず、愛犬のペースで回復させてあげましょう。
様子を見る際には、ただ時間を置くだけでなく、いくつかのポイントをチェックすることが重要です。
- 水の摂取量:ご飯は食べても、水を全く飲まない状態は脱水を引き起こすため危険です。
- 排泄の状態:おしっこやうんちが正常に出ているか、色や量、硬さに異常はないかを確認します。
- 呼びかけへの反応:名前を呼んだり、おもちゃを見せたりした時に、耳や尻尾で反応するか、視線を向けるかなど、意識の状態をチェックします。
- 歩き方:立ち上がったり歩いたりする際に、ふらつきや足を引きずる様子がないかを確認します。
これらの点を継続的に観察し、記録しておくと良いでしょう。
もし、時間の経過とともに徐々に元気を取り戻し、普段通りの様子に戻るのであれば、大きな心配はいらないケースが多いです。
しかし、「様子を見る」期間は、基本的には24時間以内が一つの目安です。
それ以上元気がない状態が続く場合や、観察している中で少しでも新たな症状が出たり、状態が悪化したりするようなら、迷わず動物病院を受診するべきです。
飼い主さんの冷静な観察が、愛犬の健康状態を正確に把握し、適切なタイミングで行動するための鍵となります。
犬が元気ないけどご飯は食べる時の正しい対処法
◆この章のポイント◆
- 動物病院へ行くべき症状のチェックポイント
- 飼い主ができる応急的な対処法
- 散歩に行きたがらない時の注意点
- 動物病院で伝えるべき大切な情報
- 犬が元気ないけどご飯は食べる時のまとめ
動物病院へ行くべき症状のチェックポイント
犬が元気ないけどご飯は食べるという状況で、様子を見るか、すぐに病院へ行くべきか、その判断は非常に重要です。
食欲があるからと油断していると、手遅れになる病気が隠れている可能性もあります。
以下に挙げる症状が一つでも見られる場合は、様子を見ずに速やかに動物病院を受診してください。
緊急性が非常に高い症状
- 呼吸が明らかに苦しそう、速い、または舌の色が紫になっている(チアノーゼ)。
- お腹が急にパンパンに膨らんできた(胃捻転の可能性)。
- ぐったりして起き上がれない、意識が朦朧としている。
- 何度も繰り返し吐き続ける、または吐こうとしても何も出ない。
- 痙攣発作が起きた、または止まらない震えがある。
- 多量の出血や、明らかな外傷がある。
- 毒物や異物を飲み込んだことが確実である。
これらの症状は、命に関わる緊急事態のサインです。
一刻も早く獣医師の処置を受ける必要があります。
できるだけ早く受診すべき症状
緊急性は上記ほどではないものの、24時間以上様子を見ずに受診を検討すべき症状もあります。
元気がない状態が24時間以上続いている場合は、一時的なものではない可能性が高いです。
また、嘔吐や下痢が複数回見られる、特に血が混じっている場合は、消化器系の重篤な問題が考えられます。
水を全く飲まない状態も、脱水症状を引き起こすため危険です。
さらに、体を触ると特定の場所を痛がる、歩き方がおかしい、おしっこが出ない、または頻繁に行くのに少量しか出ないといった症状も、病気のサインです。
これらのチェックポイントを参考に、冷静に愛犬の状態を評価し、判断に迷う場合は、ためらわずに動物病院に電話で相談することも重要です。
その際、犬の様子を具体的に伝えることで、より的確なアドバイスをもらうことができます。
飼い主さんの的確な判断と迅速な行動が、愛犬の命を救うことに繋がります。
飼い主ができる応急的な対処法
動物病院を受診するまでの間、または少し様子を見るという判断をした場合に、飼い主さんが家庭でできる応急的な対処法を知っておくことは、愛犬の負担を和らげる上で非常に重要です。
ただし、これらの対処法はあくまで獣医師の診断を受けるまでのつなぎであり、自己判断で治療を試みるものではないことを理解しておきましょう。
まず最も大切なことは、犬が安心して休める環境を整えてあげることです。
静かで、直射日光が当たらず、室温が快適に保たれた場所に、お気に入りのベッドや毛布を置いてあげましょう。
小さなお子さんや他のペットがいる場合は、できるだけ隔離して、邪魔されずに眠れるように配慮することが大切です。
次に、水分補給です。
ご飯は食べていても、水を飲んでいない場合は脱水が心配されます。
いつでも新鮮な水が飲めるようにしておくのはもちろん、もしあまり飲みたがらないようであれば、鶏のささみの茹で汁を冷まして少量与えたり、ウェットフードに少し水分を加えたりして、水分摂取を促す工夫も有効です。
ただし、嘔吐を繰り返している場合は、水分を与えることでさらに吐き気を誘発することもあるため、無理に飲ませるのは避けましょう。
食事については、食欲があるからといって、いつも通りに与えて良いとは限りません。
消化器症状が疑われる場合は、胃腸に負担をかけないように、普段の食事を少量ずつ、回数を分けて与えるのが良いでしょう。
また、消化の良いフードに一時的に切り替えるのも一つの方法です。
絶対にやってはいけないのが、人間の薬を自己判断で与えることです。
人間用の解熱鎮痛剤などは、犬にとっては中毒を引き起こす猛毒となることがあります。
良かれと思ってしたことが、かえって愛犬を危険な状態に陥れる可能性があることを、肝に銘じておきましょう。
体を温めるべきか、冷やすべきかについても注意が必要です。
震えているからといって、必ずしも寒いわけではありません。
発熱している可能性もあるため、安易に温めると逆効果になることもあります。
基本的には、犬自身が快適な場所を選べるように、部屋の中に温度差のある場所を作ってあげると良いでしょう。
これらの対処を行いながら、愛犬の状態を注意深く観察し続けることが、何よりも重要です。
散歩に行きたがらない時の注意点
普段は散歩が大好きな犬が、元気がないだけでなく、散歩に行きたがらないという行動を見せる場合、それは単なる気分の問題ではない、重要なサインである可能性があります。
犬にとって散歩は、運動欲求を満たすだけでなく、外の匂いを嗅いだり、他の犬とコミュニケーションをとったりする、精神的にも非常に重要な時間です。
その散歩を嫌がるというのは、よほどの理由があると考えられます。
まず考えられるのは、体のどこかに痛みがあるケースです。
特に足腰の痛みは、散歩を嫌がる直接的な原因になります。
椎間板ヘルニア、関節炎、骨折や捻挫などの怪我があると、歩くこと自体が苦痛になります。
リードをつけようとすると嫌がる、家の外に出てもすぐに座り込んでしまう、歩き方がぎこちないといった様子が見られたら、痛みを疑うべきです。
次に、内臓疾患による体調不良も原因として考えられます。
人間も体調が悪い時は外出する気が起きないように、犬も全身的な倦怠感や吐き気、腹痛などがあると、散歩に行く元気がなくなります。
元気がないという症状に加えて、散歩拒否が見られる場合は、見た目では分かりにくい内臓の病気が隠れている可能性も視野に入れる必要があります。
また、散歩コースで何か怖い経験をしたことが、トラウマになっている可能性もあります。
例えば、大きな工事の音に驚いた、他の犬に吠えられて怖い思いをした、車に轢かれそうになったなど、特定の場所や状況と恐怖が結びついてしまい、散歩に行くこと自体を避けるようになることがあります。
この場合は、特定の場所を避ける、特定の物音がすると怯えるといった行動が見られるかもしれません。
無理にリードを引っ張って散歩に連れて行こうとすることは、絶対に避けるべきです。
痛みを我慢させたり、恐怖心を煽ったりすることで、犬にさらなる苦痛を与えるだけでなく、飼い主さんとの信頼関係を損なうことにもなりかねません。
まずは原因を探ることが最優先です。
体を優しく触って痛がる場所がないかチェックしたり、家の外の様子を窓から見せて反応を伺ったりして、何が原因なのかを慎重に見極めましょう。
原因が特定できない、あるいは痛みが疑われる場合は、速やかに動物病院で診察を受けることが重要です。
動物病院で伝えるべき大切な情報
犬が元気ないけどご飯は食べるという状態で動物病院を受診する際、飼い主さんからの情報は、獣医師が正確な診断を下すための非常に重要な手がかりとなります。
限られた診察時間の中で、的確な情報を漏れなく伝えるために、事前に情報を整理しておくことをお勧めします。
以下の項目をメモにまとめておくと、落ち着いて説明することができます。
基本情報
- いつから元気がないのか(例:昨日の夜から、3日前からなど具体的に)
- 元気がない以外に、他に変わった様子はないか(嘔吐、下痢、咳、震え、歩き方など)
- 食欲の状態(いつも通り食べるのか、少しだけ食べるのか、おやつは食べるのかなど)
- 飲水量の変化(いつもより多い、少ない、全く飲まないなど)
- 排泄の状態(おしっこやうんちの回数、量、色、硬さの変化、血が混じっていないか)
症状に関する詳細情報
嘔吐や下痢がある場合は、その回数、時間、内容物(色、異物が混じっていないかなど)を詳しく伝えましょう。
震えや痙攣がある場合は、いつ、どのくらいの時間、体のどの部分で起きたかを説明できると良いです。
可能であれば、異常な行動(震え、苦しそうな呼吸、おかしな歩き方など)をスマートフォンで動画撮影しておくと、口で説明するよりもはるかに多くの情報が伝わります。
生活に関する情報
最近、生活環境に変化はなかったか(引っ越し、新しい家族、フードの変更など)を伝えることも重要です。
また、拾い食いの可能性や、誤飲・誤食の心当たりがあれば、正直に申告してください。
ワクチン接種やノミ・ダニ予防、フィラリア予防の状況、持病や過去の病歴、現在服用中の薬についても、正確に伝える必要があります。
これらの情報は、パズルのピースのように、それぞれが診断を組み立てる上で重要な役割を果たします。
「こんなことは関係ないだろう」と飼い主さんが判断せず、少しでも気になったことは遠慮なく獣医師に伝えるようにしましょう。
正確で詳細な情報提供が、迅速で適切な治療につながり、愛犬を苦痛から早く解放してあげることに繋がるのです。
犬が元気ないけどご飯は食べる時のまとめ
愛犬が元気ないけどご飯は食べるという状況は、飼い主さんにとって心配なサインです。
この記事では、その原因から対処法、病院へ行くべきタイミングまでを詳しく解説してきました。
最後に、重要なポイントを改めてまとめます。
この状況は、一時的な疲れやストレスから、痛みを伴う病気、内臓疾患、さらには緊急性の高い病気まで、様々な原因が考えられます。
食欲があるからといって、決して安心できるわけではありません。
最も重要なのは、元気がないという症状以外に、他に変化がないかを注意深く観察することです。
嘔吐や下痢、震え、呼吸の異常など、他の症状が見られる場合は、病気のサインである可能性が高まります。
特に高齢犬の場合は、加齢による関節の痛みや内臓機能の低下が原因であることも多いため、「年のせい」と決めつけずに、小さな変化にも気を配る必要があります。
まずは慌てずに、愛犬が安心して休める環境を整え、水分補給や排泄の状態をチェックしながら24時間ほど様子を見ることも一つの選択肢です。
しかし、症状が悪化したり、この記事で紹介した「動物病院へ行くべき症状のチェックポイント」に当てはまる項目があったりした場合は、ためらわずに獣医師の診察を受けてください。
飼い主さんの冷静な観察と、迅速で的確な判断が、愛犬の健康を守る上で最も大切です。
この記事で得た知識が、あなたと愛犬の不安を少しでも和らげ、適切な行動をとるための一助となれば幸いです。
本日のまとめ
- 犬が元気ないけどご飯は食べるのは様々な原因が考えられる
- 一時的なストレスや環境の変化も原因の一つ
- 食欲があっても病気が隠れている可能性を忘れない
- 嘔吐や下痢など他の症状の有無が重要な判断材料
- 高齢犬では関節痛や内臓疾患を特に注意する
- 痛みが原因の震えは危険なサインかもしれない
- 他に症状がなければ24時間は落ち着いて様子を見る
- 呼吸困難やぐったりしている場合は緊急性が高い
- 24時間以上元気がない状態が続けば病院へ
- 家庭ではまず安静にできる環境を整える
- 自己判断で人間の薬を与えるのは絶対にダメ
- 散歩拒否は痛みや体調不良のサインかもしれない
- 病院では症状や変化を具体的に伝えることが大事
- 異常な行動は動画で撮影しておくと診察に役立つ
- 飼い主の冷静な観察と判断が愛犬の健康を守る

愛犬の「食べない」に終止符を。手作り食レシピから生まれた『モグワン』
「せっかく買ったフードを食べてくれない…」そんな悩みを抱えていませんか?
『モグワン』は、愛犬の健康と食いつきの良さをとことん追求し、家庭での手作りごはんをヒントに誕生したプレミアムドッグフードです。
【モグワンが選ばれる3つの理由】
- 動物性タンパク源50%以上:新鮮なチキンとサーモンを贅沢に使用。封を開けた瞬間の香りが、愛犬の食欲を刺激します。
- 究極のグレインフリー:消化に負担をかける穀物を一切使わず、お腹にやさしいレシピを実現しました。
- ヒューマングレードの原材料:人間が食べる食材と同等の高品質な素材を厳選。着色料や香料も不使用で安心です。
毎日のごはんは、愛犬の体を作る大切な基盤。 「美味しそうに完食する姿が見たい」という飼い主さんの願いを、モグワンが叶えます。
今なら公式サイト限定の特別キャンペーンも実施中!まずは愛犬の驚くべき「食いつき」を体験してみませんか?
○○○○○○○○○○○○○○○○
老犬がトイレでしない原因と対策を解説!病気の可能性も
犬の愛情表現10選!行動やしぐさでわかる犬の気持ち
○○○○○○○○○○○○○○○○
参考サイト
犬の元気がないけど食欲はある時の理由とは?考えられる病気やその対処法 | わんちゃんホンポ
元気はあるのに犬がご飯を食べない理由と食べてもらう方法について – フローエンス
犬がご飯を食べない…~4つの理由と対策、病気かどうかのチェックポイント
犬の元気がない原因とは?病院に連れて行くべき症状を獣医師が解説 – PS保険
元気な犬がごはんを食べない!何日まで大丈夫?犬のワガママとの付き合い方
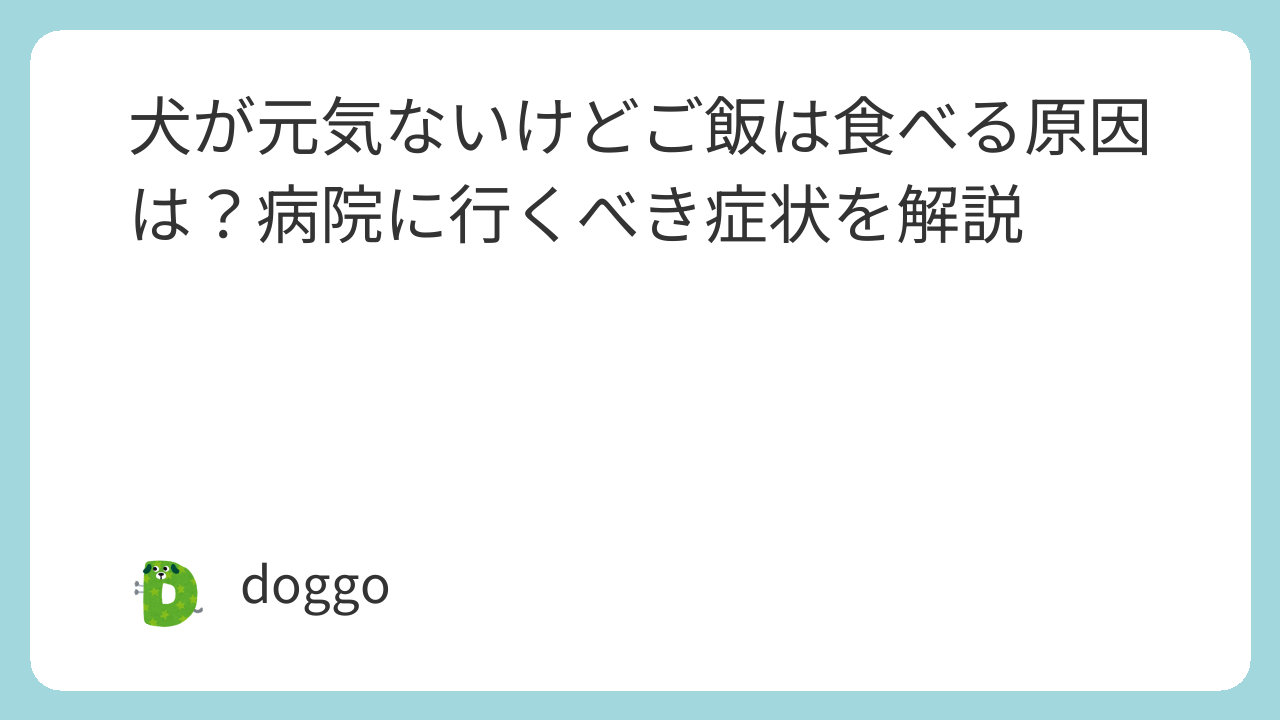
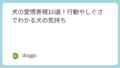
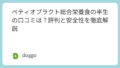
コメント