こんにちは、管理人のdoggoです
愛犬の健康を第一に考えたとき、毎日の食事管理は非常に重要なテーマとなります。
多くの飼い主さんが「うちの子に与えているドッグフードの量は本当に適切だろうか」という疑問を一度は抱いたことがあるのではないでしょうか。
犬の食事量目安は、ただパッケージの裏に書かれている量を与えるだけでは不十分な場合があります。
なぜなら、犬の必要とするカロリーは、その犬の体重や年齢、ライフステージによって大きく異なるからです。
また、運動量や健康状態、さらには避妊・去勢手術の有無によっても、適切な食事の回数や種類を見直す必要があります。
もし愛犬がご飯を急に食べないといった状況になれば、飼い主さんとしては心配になりますし、その原因と対処法を知っておきたいものでしょう。
この記事では、そうした飼い主さんのあらゆる疑問や悩みに応えるため、犬の食事量目安に関する情報を網羅的に解説していきます。
正しい計算方法から、具体的な状況に合わせた調整のポイントまで、愛犬の健康を支えるための知識を深めていきましょう。
◆このサイトでわかる事◆
- 犬の食事量目安の基本的な計算方法
- 体重や年齢に応じた食事量の調整ポイント
- ライフステージ別の適切な食事回数
- フードの種類による給与量の違い
- 避妊・去勢手術後の食事管理の注意点
- 愛犬がご飯を食べないときの原因と対策
- 健康状態に合わせた食事量の考え方

驚きの食いつき!愛犬が夢中になる『カナガン』で、真の健康を。
「最近ごはんの食べが悪い」「本当に安心できるものを与えたい」……そんな飼い主さんの悩みを解決するのが、世界中の愛犬家に選ばれている『カナガン』です。
【カナガンが支持される3つのこだわり】
- お肉・お魚が50%以上の高配合:新鮮なチキンやサーモンを贅沢に使用。良質なタンパク質が、愛犬の健康な筋肉と活力ある毎日をサポートします。
- 穀物不使用(グレインフリー):ワンちゃんが消化しにくいトウモロコシや小麦を一切排除。お腹にやさしく、アレルギーが気になる子にも安心です。
- 全年齢・全犬種対応の小粒サイズ:ドーナツ型の小さな粒は、子犬や小型犬でも噛み砕きやすく、サクサクとした食感で食欲をそそります。
「ごはんの時間が待ち遠しそう!」「毛並みのツヤが楽しみになった」と喜びの声も続々。 イギリスの厳しい基準をクリアした最高級の美味しさで、愛犬の瞳を輝かせてみませんか?
犬の食事量目安を計算する方法
◆この章のポイント◆
- まずは必要カロリーの計算から
- 体重別のドッグフード量の違い
- 年齢に合わせた量の調整
- ライフステージごとの見直し
- 食事の回数も重要な要素
まずは必要カロリーの計算から
犬の食事量目安を正確に把握するための第一歩は、愛犬が1日に必要とするカロリーを知ることから始まります。
このカロリー計算には、専門的な二つの指標、「安静時エネルギー要求量(RER)」と「1日あたりのエネルギー要求量(DER)」が用いられるのです。
一見すると難しそうに聞こえるかもしれませんが、計算式自体はシンプルなので、ぜひこの機会に覚えてみましょう。
まず、安静時エネルギー要求量(RER)とは、犬が健康的な状態で、静かで快適な環境で過ごしているときに必要とする最低限のエネルギー量を指します。
これは生命維持に不可欠なカロリーであり、すべての計算の基礎となる数値です。
RERは以下の計算式で求めることができます。
安静時エネルギー要求量(RER)の計算式
RER(kcal/日) = 70 × (体重kg)の0.75乗
電卓を使う場合は、「体重(kg) × 体重(kg) × 体重(kg) = 」のあとに「√」キーを2回押し、その数値に70を掛けると簡単に計算できます。
例えば、体重5kgの犬であれば、RERは約234kcalとなります。
次に、このRERをもとに、1日あたりのエネルギー要求量(DER)を算出します。
DERは、RERに犬の年齢や活動レベル、避妊・去勢の有無などを考慮した「係数」を掛けて求められるものです。
つまり、DERこそが、愛犬が1日に本当に必要とする総カロリー量を示しています。
1日あたりのエネルギー要求量(DER)の計算式
DER(kcal/日) = RER × 係数
この「係数」は犬の状態によって細かく分かれています。
以下に代表的な係数の目安をまとめましたので、ご自身の愛犬がどれに当てはまるか確認してみてください。
| 犬の状態 | 係数 |
|---|---|
| 成長期(生後4ヶ月まで) | 3.0 |
| 成長期(生後4ヶ月以降) | 2.0 |
| 未避妊・未去勢の成犬 | 1.8 |
| 避妊・去勢済みの成犬 | 1.6 |
| 肥満傾向・運動量の少ない犬 | 1.2~1.4 |
| 減量が必要な犬 | 1.0 |
| 高齢犬(7歳以上) | 1.1~1.4 |
| 活動犬・ワーキングドッグ | 2.0~5.0 |
例えば、先ほどの体重5kgで避妊手術済みの成犬の場合、DERは「234kcal (RER) × 1.6 = 374.4kcal」となります。
これが、その犬が1日に摂取すべきカロリーの目安です。
このDERを基準にドッグフードのパッケージに記載されているカロリー量(例:350kcal/100g)を確認し、1日あたりの給与グラム数を割り出すことが、正しい犬の食事量目安を知るための最も正確な方法と言えるでしょう。
体重別のドッグフード量の違い
愛犬の1日に必要なカロリー(DER)が分かったら、次はいよいよ具体的なドッグフードの給与量を計算する段階に進みます。
多くの飼い主さんはドッグフードのパッケージに記載されている給与量を目安にしていると思いますが、あれはあくまで標準的なモデルケースです。
より愛犬に合った量を与えるためには、DERとフードのカロリーを基にした計算が欠かせません。
計算方法は非常にシンプルです。
ドッグフード給与量の計算式
1日の給与量(g) = DER(kcal) ÷ ドッグフード100gあたりのカロリー(kcal) × 100
例えば、DERが374.4kcalの犬に、100gあたり350kcalのドライフードを与える場合を考えてみましょう。
計算式に当てはめると、「374.4 ÷ 350 × 100 ≒ 107g」となります。
つまり、この犬には1日あたり約107gのフードを与えるのが適切ということになります。
この計算を行う上で重要なのが、必ず与えているドッグフードの正確なカロリー量を確認することです。
ドッグフードは製品によってカロリーが大きく異なり、高カロリーなものもあれば、低カロリーなものもあります。
パッケージの成分表示欄に「代謝エネルギー」として「〇〇kcal/100g」のように記載されているので、必ずチェックしてください。
体重が同じ犬であっても、個体差によって必要カロリーは変動します。
例えば、同じ5kgの犬でも、犬種によって骨格や筋肉量が違うため、基礎代謝が異なります。
また、散歩の時間や室内での活動量など、ライフスタイルによっても消費カロリーは変わってくるでしょう。
したがって、計算で出した給与量はあくまでスタートラインと考えることが大切です。
実際に与え始めた後は、定期的に愛犬の体重を測定し、体型をチェックする習慣をつけましょう。
理想的な体型は、肋骨(あばら骨)が薄い脂肪の層の下に手で触れて感じられ、上から見たときに腰にくびれが見える状態です。
もし体重が増え続けるようであれば給与量を5~10%減らし、逆に痩せてくるようであれば少し増やすなど、微調整を行ってください。
このように、計算と観察を繰り返すことが、愛犬にとってのベストな食事量を見つけるための鍵となります。
年齢に合わせた量の調整
犬の食事量目安を考える上で、年齢は非常に重要な要素です。
人間が成長期の子ども、働き盛りの大人、そして落ち着いた高齢者で食事内容が変わるように、犬もライフステージに応じて必要とする栄養素やカロリーが大きく変化します。
ここでは「子犬期」「成犬期」「高齢犬期(シニア期)」の3つのステージに分けて、食事量調整のポイントを解説します。
子犬期(~約1歳)
子犬期は、骨格や筋肉、内臓など、体全体が急速に成長する最も重要な時期です。
そのため、成犬の2~3倍ものカロリーと、豊富なタンパク質、カルシウム、ミネラルなどを必要とします。
この時期の栄養不足は、将来的な健康問題に直結しかねません。
食事量は、少量ずつを頻繁に与えるのが基本です。
胃がまだ小さく、一度に多くの量を消化できないため、生後3ヶ月頃までは1日3~4回、それ以降は1日2~3回に分けて与えるのが一般的です。
フードは必ず「子犬用」や「パピー用」と記載された、成長期に必要な栄養バランスが調整されたものを選んでください。
成犬期(約1歳~7歳)
成犬期は、成長が止まり、体格が安定する時期です。
この時期の食事管理の目的は、健康的な体重と体型を維持することにあります。
カロリーの与えすぎは肥満につながり、関節疾患や糖尿病、心臓病などのリスクを高めてしまいます。
前述のDER計算を基に、愛犬の活動量や体質に合わせた適切な食事量を守ることが重要です。
食事回数は1日1~2回が一般的ですが、早食いや胃腸が弱い犬の場合は、2回に分けた方が負担が少ないでしょう。
特に小型犬は低血糖になりやすいため、1日2回の食事を推奨します。
高齢犬期(シニア期、約7歳~)
犬も7歳頃からシニア期に入り、徐々に体に変化が現れ始めます。
基礎代謝が低下し、運動量も減ってくるため、成犬期と同じ量の食事を与えていると太りやすくなります。
そのため、成犬期に比べて10~20%ほどカロリーを抑えた食事が推奨されます。
また、消化機能の低下や、関節・心臓・腎臓などの健康維持に配慮した栄養素が必要になるため、「シニア用」「高齢犬用」のフードに切り替えるのが望ましいでしょう。
食事回数は、消化の負担を軽減するために1日2~3回に分けて与えるのがおすすめです。
年齢はあくまで目安であり、犬種や個体によって老化のスピードは異なります。
愛犬の様子をよく観察し、活動量の変化や体型の変化に合わせて、食事内容を柔軟に見直していくことが大切です。
ライフステージごとの見直し
犬の食事量目安は、一度決めたらそれで終わりというわけではありません。
犬は人間よりもずっと早いスピードで歳をとり、そのライフステージごとに体は大きな変化を遂げます。
子犬期、成犬期、シニア期という大まかな区分だけでなく、より細かいイベントに合わせて食事内容を見直すことが、愛犬の生涯にわたる健康を支える上で不可欠です。
例えば、成犬期の中にも特別な配慮が必要な時期があります。
妊娠・授乳期の母犬
妊娠・授乳期の母犬は、お腹の中の子犬を育て、そして母乳を作るために、通常よりもはるかに多くのエネルギーと栄養を必要とします。
特に授乳期は、必要カロリーが通常の3~4倍にも達することがあるのです。
この時期は、高タンパク・高カロリーな「子犬用」や「マザー&ベビー用」のフードに切り替え、食事量も徐々に増やしていく必要があります。
食事回数も1日3~4回に増やし、母犬がいつでも栄養を補給できるようにしてあげましょう。
活動レベルの変化
家庭犬であっても、ライフスタイルの変化によって活動レベルが変わることがあります。
例えば、ドッグスポーツを始めたり、日常的に長時間の散歩やハイキングに出かけるようになったりした場合、消費カロリーは増加します。
このような場合は、体重が減少しないか注意深く観察し、必要に応じて食事量を10~20%程度増やすか、より高カロリーな「アクティブドッグ用」のフードを検討するのも良いでしょう。
逆に、飼い主の仕事の都合で散歩の時間が短くなったり、犬が怪我をして運動制限が必要になったりした場合は、食事量を減らさなければ肥満につながります。
ライフステージの変化に合わせて食事を見直すことは、将来の病気を予防するための重要な投資です。
特にシニア期への移行は緩やかに進むため、飼い主さんが「最近、散歩で疲れやすくなったかな?」「寝ている時間が増えたかな?」といった小さなサインに気づいてあげることが大切です。
定期的な体重測定とボディコンディションスコア(BCS)による体型チェックを習慣化し、変化が見られたら食事量やフードの種類を見直すように心がけましょう。
判断に迷う場合は、かかりつけの獣医師に相談するのが最も確実です。
食事の回数も重要な要素
犬の食事量目安を考えるとき、1日に与える総量だけでなく、「何回に分けて与えるか」という食事の回数も、健康維持において非常に重要な要素となります。
適切な食事回数は、犬の年齢や体の大きさ、健康状態によって異なり、消化器系への負担や満足感、さらには問題行動の予防にも関わってきます。
ライフステージ別の適切な回数の目安は以下の通りです。
子犬期(~約1歳)
子犬は体が小さい上に消化器官が未発達なため、一度にたくさんの量を食べることができません。
しかし、成長のためには多くのカロリーを必要とします。
このギャップを埋めるため、1日の食事量を複数回に分けて与えるのが基本です。
- 生後2~3ヶ月頃まで:1日3~4回
- 生後6ヶ月頃まで:1日3回
- 生後6ヶ月以降:1日2~3回
特に小型犬の子犬は空腹時間が長くなると低血糖を起こしやすいので、こまめに食事を与えることが重要です。
成犬期(約1歳~7歳)
成犬の場合、食事回数は1日1回または2回が一般的です。
どちらが良いかは犬の個体差やライフスタイルによりますが、獣医学的には1日2回に分けて与えることが推奨される傾向にあります。
その理由として、空腹時間が長くなりすぎると、胃酸過多で嘔吐(胆汁嘔吐症候群)しやすくなったり、1回の食事量が多くなることで胃拡張・胃捻転のリスクが高まったりすることが挙げられます。
特に胸の深い大型犬(グレートデン、ドーベルマンなど)は胃捻転のリスクが高いため、1日2回以上の分割給与が望ましいでしょう。
また、食事を2回に分けることで、犬の満足感が高まり、空腹によるストレスを軽減できるというメリットもあります。
高齢犬期(シニア期、約7歳~)
シニア犬は、加齢とともに消化機能が低下してきます。
一度に多くの量を食べると、消化不良や嘔吐の原因になることがあります。
そのため、1回の食事量を減らし、その分回数を増やしてあげるのが理想的です。
1日の総量を2~3回、場合によっては4回に分けて与えることで、消化器への負担を軽減し、安定した栄養吸収を助けることができます。
食事の時間を決めることも大切です。
毎日なるべく同じ時間に食事を与えることで、犬の体内リズムが整い、消化液の分泌も安定します。
散歩の前に食事をすると胃捻転のリスクを高める可能性があるため、食後しばらくは安静にさせるようにしてください。
食事の回数を見直すことは、愛犬のQOL(生活の質)を向上させる簡単な方法の一つです。
愛犬の年齢や様子をよく観察し、最適な回数を見つけてあげましょう。
状況に応じた犬の食事量目安の調整
◆この章のポイント◆
- フードの種類による量の違い
- 避妊・去勢手術後の注意点
- 愛犬がご飯を食べない時の対処法
- 健康状態で食事量は変わる
- 愛犬の健康を守る犬の食事量目安のまとめ
フードの種類による量の違い
犬の食事量目安を考える際、与えているドッグフードの種類は給与量を決定する上で極めて重要な要素です。
ドッグフードは、その水分含有量によって大きく「ドライフード」「ウェットフード」「セミモイストフード」などに分類され、それぞれ栄養価やカロリー密度が全く異なります。
同じグラム数でも、フードの種類が違えば摂取カロリーは大きく変わってしまうため、フードを切り替える際には特に注意が必要です。
ドライフード
最も一般的で、多くの家庭で主食として利用されているのがドライフードです。
水分含有量が10%程度と低く、栄養が凝縮されているため、少ない量で効率的にエネルギーを摂取できます。
長期保存が可能でコストパフォーマンスに優れ、硬い粒を噛むことで歯石が付きにくいというメリットもあります。
カロリーは製品によって様々ですが、一般的には100gあたり350~400kcal程度のものが多いでしょう。
ウェットフード
缶詰やパウチに入ったウェットフードは、水分含有量が75%以上と非常に高いのが特徴です。
そのため、ドライフードと同じグラム数を与えても、摂取できるカロリーは大幅に少なくなります。
一般的にウェットフードは100gあたり100kcal前後と、ドライフードの約1/4程度のカロリーです。
嗜好性が高く、食欲が落ちた犬でも食べてくれやすいのが最大のメリットと言えるでしょう。
また、食事から自然に水分を補給できるため、水をあまり飲まない犬や、泌尿器系の疾患が気になる犬にも適しています。
セミモイストフード・ソフトドライフード
ドライフードとウェットフードの中間的な性質を持つのが、セミモイストフードやソフトドライフードです。
水分含有量は25~35%程度で、しっとりとした食感が特徴です。
ドライフードよりも嗜好性が高い一方で、ウェットフードよりは日持ちがします。
カロリーは100gあたり300kcal前後のものが多く、ドライフードよりはやや低めです。
フードを切り替える際の注意点として、必ずそれぞれのフードのカロリーを確認し、再計算することが挙げられます。
例えば、今までドライフードを100gあげていたからといって、ウェットフードも100g与えてしまうと、カロリーが大幅に不足してしまいます。
逆に、ウェットフードからドライフードに切り替える際に同じ感覚で与えると、カロリーオーバーで肥満の原因になります。
異なる種類のフードを混ぜて与える「ミックスフィーディング」を行う場合も、それぞれのフードの量とカロリーを正確に計算し、1日の総摂取カロリー(DER)を超えないように管理することが重要です。
避妊・去勢手術後の注意点
愛犬の健康や望まない繁殖を防ぐために、多くの犬が避妊手術(メス)や去勢手術(オス)を受けます。
この手術は犬の体に大きな変化をもたらしますが、特に影響が大きいのが「ホルモンバランスの変化」とそれに伴う「エネルギー要求量の低下」です。
手術後の食事管理を怠ると、肥満になるリスクが非常に高まるため、飼い主さんは犬の食事量目安を再設定する必要があります。
手術によって性ホルモンの分泌がなくなると、一般的に基礎代謝が低下します。
研究によっては、手術前に比べてエネルギー要求量が20~30%も減少するという報告もあるほどです。
つまり、手術前と同じ量の食事を与えていると、消費しきれなかったエネルギーが脂肪として蓄積されやすくなるのです。
さらに、性ホルモンには食欲を抑制する働きもあったため、手術後は食欲が増進する傾向が見られます。
「代謝が落ちて消費カロリーは減るのに、食欲は増す」という、非常に太りやすい状態に陥ってしまうわけです。
この変化に対応するため、手術後は食事内容の見直しが必須となります。
食事量の調整
まず、1日に与える食事の総量を減らす必要があります。
目安として、手術前の食事量から10~20%程度減らすことから始めてみましょう。
前述のDER(1日あたりのエネルギー要求量)の計算式を思い出してください。
未避妊・未去勢の成犬の係数が「1.8」であったのに対し、避妊・去勢済みの成犬の係数は「1.6」でした。
この係数の違いが、まさに手術によるエネルギー要求量の低下を反映しています。
手術後は、係数「1.6」を使ってDERを再計算し、適切な給与量を算出することが最も確実な方法です。
フードの切り替え
食事量を減らすと、犬が満腹感を得られずに食事を催促することがあります。
その場合は、フード自体の見直しを検討しましょう。
市場には「避妊・去勢後用」の専用フードが数多く販売されています。
これらのフードは、通常のフードよりも低カロリー・低脂肪でありながら、満腹感を得やすいように食物繊維が豊富に含まれているのが特徴です。
また、筋肉量を維持するための良質なタンパク質や、健康維持に必要なビタミン・ミネラルがバランス良く配合されています。
手術後は、こうした専用フードに切り替えることで、食事の満足感を損なわずに体重管理がしやすくなります。
手術後の体重管理は、術後2~3ヶ月が特に重要と言われています。
この時期に体重が増加傾向にある場合は、早めに食事内容を見直し、適切な運動を取り入れることで、将来の肥満や関連疾患のリスクを大幅に減らすことができます。
愛犬がご飯を食べない時の対処法
毎日喜んでご飯を食べていた愛犬が、急にフードを食べなくなると、飼い主さんとしては非常に心配になるものです。
犬が食欲不振になる原因は様々で、一時的なわがままから、深刻な病気のサインである可能性まで考えられます。
まずは慌てずに、愛犬の様子をよく観察し、原因を探ることが大切です。
考えられる主な原因は以下の通りです。
- 病気や体調不良:消化器系の病気、歯周病などの口内の痛み、感染症、内臓疾患など、様々な病気が食欲不振を引き起こします。元気がない、嘔吐や下痢がある、水を飲まないなど、他の症状も見られる場合は、すぐに動物病院を受診してください。
- ストレス:引っ越し、家族構成の変化、長時間の留守番、雷や花火の音など、環境の変化やストレスが原因で食欲が落ちることがあります。
- わがまま・フードへの飽き:おやつをもらいすぎてお腹がいっぱいだったり、同じフードに飽きてしまったりして食べないことがあります。また、「フードを食べなければ、もっと美味しいものがもらえる」と学習してしまっているケースも考えられます。
- 加齢による変化:シニア犬になると、運動量の低下に伴い食欲が自然と落ちることがあります。また、嗅覚が衰えてフードの匂いを感じにくくなることも一因です。
原因に応じて、以下のような対処法を試してみましょう。
フードに工夫を凝らす
一時的な飽きやわがままが原因の場合、フードの嗜好性を高める工夫が有効です。
まず試したいのが、フードを少し温めることです。
人肌程度に温めることで香りが立ち、犬の食欲を刺激します。
ドライフードであれば、ぬるま湯でふやかしてあげるのも良い方法です。
また、ウェットフードや犬用のふりかけ、茹でたササミや野菜などを少量トッピングしてあげるのも効果的でしょう。
ただし、トッピングの与えすぎは栄養バランスの乱れや、トッピングしか食べなくなる原因にもなるため、あくまで少量に留めることが大切です。
食事環境を見直す
犬は安心して食事ができる環境を好みます。
食器の場所が騒がしい、他の犬に邪魔される、食器の高さが合っていないなどの理由で、食事がストレスになっている可能性もあります。
静かで落ち着ける場所に食器を移動したり、食べやすい高さの食器台を用意したりするなど、環境を整えてあげましょう。
わがままへの対応
もし健康状態に問題がなく、単なるわがままで食べていないようであれば、心を鬼にして一定時間(15~20分程度)で食器を片付けるという方法もあります。
「出された時に食べなければ、次の食事まで何もない」ということを学習させるためです。
ただし、この方法は子犬や病気の犬には行わないでください。
最も重要なのは、食欲不振以外の症状がないかを確認することです。
元気や食欲が24時間以上戻らない場合や、嘔吐、下痢、ぐったりしているなどの異常が見られる場合は、自己判断せず、速やかに獣医師の診察を受けましょう。
健康状態で食事量は変わる
犬の食事量目安は、愛犬の健康状態によって大きく左右されます。
特定の病気を患っている場合や、体質的に配慮が必要な場合、獣医師の指導のもとで食事内容を厳密に管理する「食事療法(栄養療法)」が必要になることがあります。
食事療法は、薬物治療と並行して行われる重要な治療の一環であり、病気の進行を遅らせたり、症状を緩和させたりする効果が期待できます。
食事管理が特に重要となる代表的な健康状態をいくつかご紹介します。
肥満
肥満は万病のもとと言われ、関節疾患、糖尿病、心臓病、呼吸器疾患など、様々な病気のリスクを高めます。
肥満の犬には、獣医師の指導のもとで減量プログラムを実施する必要があります。
これには、低カロリー・高繊維で満腹感を得やすい「減量用」の療法食を用い、正確に計量した食事を計画的に与えることが含まれます。
急激な減量は犬の体に負担をかけるため、1週間に体重の1~2%を減らすペースで、時間をかけて行うのが一般的です。
腎臓病
慢性腎臓病は、特に高齢の犬に多く見られる病気です。
腎臓の機能が低下すると、体内の老廃物をうまく排出できなくなります。
そのため、腎臓に負担をかけるタンパク質やリン、ナトリウムの摂取を制限した専用の療法食が必要となります。
腎臓病の食事療法は、病気の進行をコントロールし、犬の生活の質を維持するために不可欠です。
食物アレルギー
特定の食べ物に含まれるタンパク質に対して免疫が過剰反応し、皮膚の痒みや下痢、嘔吐などの症状を引き起こすのが食物アレルギーです。
原因となるアレルゲンを特定し、それを食事から除去する必要があります。
アレルギー対応の療法食には、アレルゲンとなりやすいタンパク質(牛肉、鶏肉、乳製品など)を含まないフードや、タンパク質をあらかじめ分解してアレルギー反応を起こしにくくした「加水分解タンパク」を使用したフードなどがあります。
糖尿病
糖尿病の犬は、血糖値のコントロールが重要になります。
食事療法では、食後の急激な血糖値の上昇を抑えるために、食物繊維が豊富に含まれ、糖質の吸収が穏やかな専用のフードが用いられます。
また、インスリン注射と連携して、毎日決まった時間に決まった量の食事を与えることが、血糖値を安定させる上で非常に重要です。
これらの療法食は、特定の栄養素が制限または強化された特別なフードであり、健康な犬に与えると栄養バランスが崩れる可能性があります。
必ず獣医師の診断と処方に従って使用してください。
愛犬に何らかの持病がある場合や、健康診断で異常を指摘された場合は、自己判断でフードを選ばず、まずはかかりつけの獣医師に相談し、その子に最適な食事プランを立ててもらうことが何よりも大切です。
愛犬の健康を守る犬の食事量目安のまとめ
これまで、犬の食事量目安に関する様々な側面について詳しく解説してきました。
愛犬の健康を維持し、幸せな毎日を共に過ごすためには、飼い主さんが食事管理に関する正しい知識を持つことが不可欠です。
最後に、この記事の重要なポイントをまとめて振り返ってみましょう。
犬の食事量目安の基本は、まず愛犬の1日に必要なカロリー、すなわちDER(1日あたりのエネルギー要求量)を計算することから始まります。
このDERは、犬の体重、年齢、活動レベル、そして避妊・去勢の有無などを考慮した係数を用いて算出される、非常に個別性の高い指標です。
計算で導き出されたカロリーと、与えているドッグフードのパッケージに記載されている100gあたりのカロリーを基に、1日の正しい給与グラム数を割り出すことができます。
しかし、計算で出た数値はあくまで出発点に過ぎません。
子犬期、成犬期、シニア期といったライフステージの変化や、妊娠・授乳、活動レベルの変動など、様々な状況に応じて食事内容は柔軟に見直す必要があります。
特に、避妊・去勢手術後は代謝が落ちて太りやすくなるため、食事量を減らすか、専用のフードに切り替えるといった対策が重要です。
また、ドライフードとウェットフードではカロリー密度が大きく異なるため、フードの種類を変える際には必ず給与量を再計算しなければなりません。
もし愛犬がご飯を食べないときは、病気の可能性も視野に入れつつ、フードに工夫を凝らしたり、ストレスの原因を取り除いたりするなどの対処が求められます。
そして、肥満や腎臓病、アレルギーといった特定の健康問題を抱えている場合は、獣医師の指導のもとで療法食を用いた厳密な食事管理が必要となります。
最も大切なのは、計算だけに頼るのではなく、日々愛犬の体をよく見て、触って、その変化に気づいてあげることです。
定期的な体重測定と、肋骨の触り具合や腰のくびれを確認するボディコンディションスコア(BCS)を習慣にしましょう。
愛犬にとっての最適な食事量は、飼い主さんの愛情深い観察と、科学的な知識の両方があって初めて見つかるものなのです。
この記事で得た知識を活かし、愛犬との健やかで長い暮らしを実現するための一助としていただければ幸いです。
本日のまとめ
- 犬の食事量目安はDER(1日あたりのエネルギー要求量)で計算する
- DERの計算には体重・年齢・活動レベルなどを考慮した係数が必要
- 計算したカロリーとフードのカロリーから1日の給与グラム数を算出
- 子犬期は高カロリーな食事を1日3~4回に分けて与える
- 成犬期は健康体重維持が目的で食事回数は1日1~2回が基本
- シニア期は低カロリーな食事を消化の負担が少ないよう2~3回に分ける
- ドライフードとウェットフードではカロリーが全く違うため注意が必要
- 避妊・去勢後は太りやすいため食事量を1~2割減らすか専用フードに
- 犬がご飯を食べない原因は病気・ストレス・わがままなど様々
- 食欲不振が続く場合や他の症状がある場合は動物病院へ
- 肥満や腎臓病などの場合は獣医師の指導のもと療法食で管理する
- 計算値はあくまで目安であり個体差があることを理解する
- 定期的な体重測定とボディコンディションスコアの確認が重要
- 食事量は固定せず愛犬の状態に合わせて柔軟に見直す
- 正しい食事管理は愛犬の健康寿命を延ばすための愛情表現である

驚きの食いつき!愛犬が夢中になる『カナガン』で、真の健康を。
「最近ごはんの食べが悪い」「本当に安心できるものを与えたい」……そんな飼い主さんの悩みを解決するのが、世界中の愛犬家に選ばれている『カナガン』です。
【カナガンが支持される3つのこだわり】
- お肉・お魚が50%以上の高配合:新鮮なチキンやサーモンを贅沢に使用。良質なタンパク質が、愛犬の健康な筋肉と活力ある毎日をサポートします。
- 穀物不使用(グレインフリー):ワンちゃんが消化しにくいトウモロコシや小麦を一切排除。お腹にやさしく、アレルギーが気になる子にも安心です。
- 全年齢・全犬種対応の小粒サイズ:ドーナツ型の小さな粒は、子犬や小型犬でも噛み砕きやすく、サクサクとした食感で食欲をそそります。
「ごはんの時間が待ち遠しそう!」「毛並みのツヤが楽しみになった」と喜びの声も続々。 イギリスの厳しい基準をクリアした最高級の美味しさで、愛犬の瞳を輝かせてみませんか?
○○○○○○○○○○○○○○○○
鬼怒川湯わんの口コミを徹底解説!愛犬と泊まる宿の評判は?
犬伝染性肝炎の原因を徹底解説!症状や予防法も紹介
○○○○○○○○○○○○○○○○
参考サイト
1日の適切なドッグフード量は?計算方法や回数、タイミング、注意点まで – OZmall
【獣医師監修】犬のごはんの量はどう決める?計算方法や目安について – どうぶつ病院宅配便
ドッグフードの与え方- K9ナチュラル
食事の適量はどうやって見分けるの?|愛犬のためにできること – プロマネージ
ドッグフードの正しい与え方と注意点【獣医師監修】 – となりのカインズさん
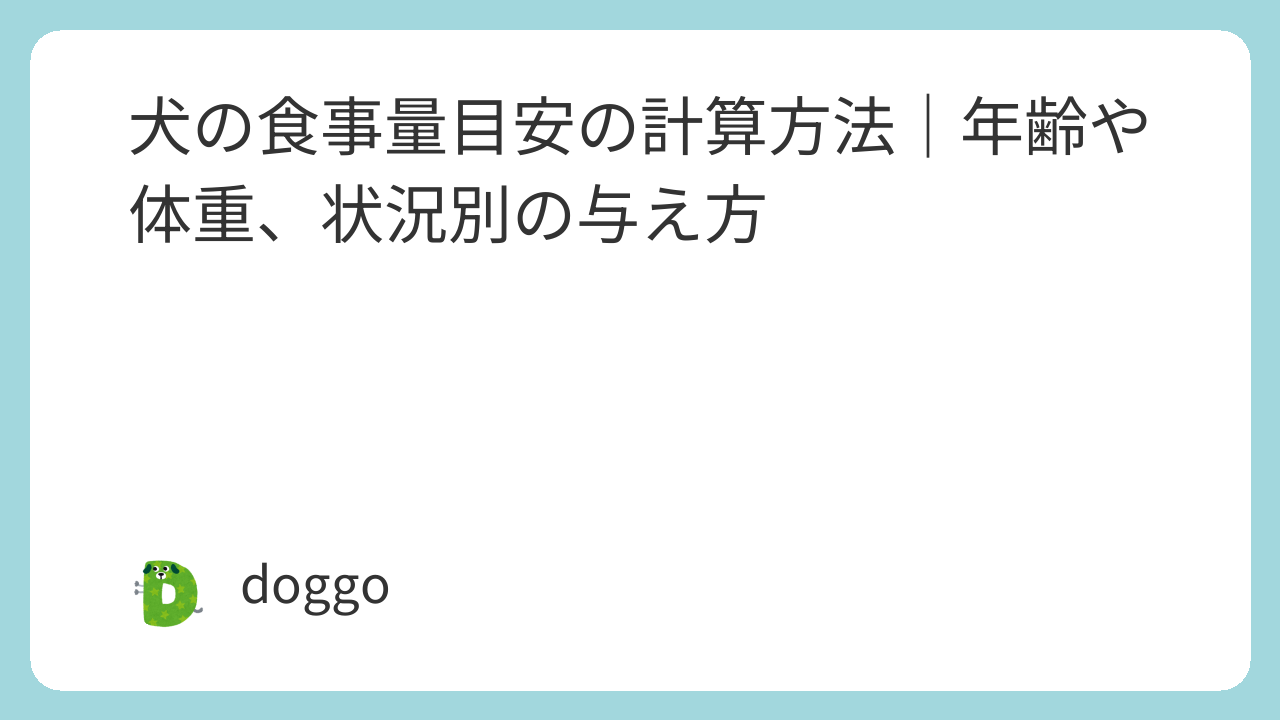
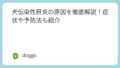
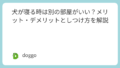
コメント