こんにちは、管理人のdoggoです
愛犬の健康は、飼い主にとって何よりも大切なことではないでしょうか。
しかし、犬たちの周りには目に見えない多くの脅威が存在します。
その一つが、時に命に関わることもある「犬伝染性肝炎」という病気です。
この記事では、犬伝染性肝炎の原因について深く掘り下げ、その正体であるウイルスの特徴から、どのような感染経路で広がるのか、そして感染した場合に現れる具体的な症状について詳しく解説を進めていきます。
特に子犬やワクチン未接種の犬にとっては非常に危険な病気であり、突然死に至るケースも報告されています。
潜伏期間中の様子や、回復期に見られるブルーアイといった特有の症状についても触れていきます。
さらに、現在のところ確立された治療法がない中で、私たち飼い主ができる最善の対策、すなわちワクチン接種による予防の重要性や、感染拡大を防ぐための具体的な方法まで、網羅的に情報をお届けします。
この記事を最後まで読むことで、犬伝染性肝炎の原因を正しく理解し、愛犬をこの恐ろしい病気から守るための知識を身につけることができるでしょう。
◆このサイトでわかる事◆
- 犬伝染性肝炎を引き起こすウイルスの正体
- 主な感染経路と潜伏期間
- 注意すべき初期症状と特有の症状ブルーアイ
- 子犬が特に重症化しやすい理由
- 確立された治療法がないという現状
- 最も効果的な予防法であるワクチン接種の重要性
- 家庭でできる感染拡大の防止策

愛犬の「食べない」に終止符を。手作り食レシピから生まれた『モグワン』
「せっかく買ったフードを食べてくれない…」そんな悩みを抱えていませんか?
『モグワン』は、愛犬の健康と食いつきの良さをとことん追求し、家庭での手作りごはんをヒントに誕生したプレミアムドッグフードです。
【モグワンが選ばれる3つの理由】
- 動物性タンパク源50%以上:新鮮なチキンとサーモンを贅沢に使用。封を開けた瞬間の香りが、愛犬の食欲を刺激します。
- 究極のグレインフリー:消化に負担をかける穀物を一切使わず、お腹にやさしいレシピを実現しました。
- ヒューマングレードの原材料:人間が食べる食材と同等の高品質な素材を厳選。着色料や香料も不使用で安心です。
毎日のごはんは、愛犬の体を作る大切な基盤。 「美味しそうに完食する姿が見たい」という飼い主さんの願いを、モグワンが叶えます。
今なら公式サイト限定の特別キャンペーンも実施中!まずは愛犬の驚くべき「食いつき」を体験してみませんか?
ウイルスが引き起こす犬伝染性肝炎の原因とは
◆この章のポイント◆
- 原因は犬アデノウイルス1型という存在
- 主な感染経路は尿や唾液からの接触
- 感染後の潜伏期間は4日から7日程度
- 子犬は特に重症化しやすく突然死のリスクも
- 発熱や嘔吐など注意すべき初期症状
原因は犬アデノウイルス1型という存在
犬伝染性肝炎の原因は、犬アデノウイルス1型(Canine Adenovirus type 1、略してCAV-1)と呼ばれる特定のウイルスへの感染です。
このウイルスは非常に小さく、肉眼で見ることはもちろんできませんが、犬の体内に侵入すると深刻な健康被害を引き起こす力を持っています。
主に肝臓の細胞に感染し、そこで増殖することで肝臓に炎症、すなわち肝炎を引き起こすことが、この病気の名前の由来となっています。
しかし、犬アデノウイルス1型の影響は肝臓だけにとどまるものではありません。
このウイルスは血管の内側を覆う血管内皮細胞にも感染する性質があり、そのため全身のさまざまな臓器に出血や炎症をもたらす可能性があるのです。
具体的には、腎臓、脾臓、肺、そして眼など、血液が巡るあらゆる場所で問題を起こすと考えられています。
特に眼に影響が及んだ場合、回復期に「ブルーアイ」と呼ばれる角膜の白濁が見られることがあり、これは犬伝染性肝炎のひとつの特徴的な症状として知られています。
犬アデノウイルスにはいくつかの種類があり、例えば犬アデノウイルス2型(CAV-2)は、一般的に「ケンネルコフ」として知られる犬の伝染性気管気管支炎の原因ウイルスのひとつです。
1型と2型は異なる病気を引き起こしますが、互いに似た構造を持っているため、2型のワクチンを接種することで1型への感染も防ぐことができる交差免疫という現象が成り立ちます。
現在の混合ワクチンでは、呼吸器への影響が少ない2型ウイルスが、犬伝染性肝炎の予防目的で広く利用されています。
このウイルスは非常に感染力が強く、また環境中でも比較的長く生存する能力を持っています。
そのため、感染した犬との直接的な接触がなくても、ウイルスに汚染された環境から感染する可能性がある点には注意が必要でしょう。
犬伝染性肝炎の原因となる犬アデノウイルス1型は、肝臓だけでなく全身の血管にも影響を及ぼす危険なウイルスなのです。
このウイルスの性質を正しく理解することが、愛犬を病気から守るための第一歩と言えるでしょう。
主な感染経路は尿や唾液からの接触
犬伝染性肝炎の主な感染経路は、ウイルスに感染した犬の体液や排泄物との接触によるものです。
犬アデノウイルス1型は、感染した犬の尿、唾液、そして糞便などに大量に含まれて排出されます。
特に尿中には、回復後も数ヶ月(長い場合は6ヶ月以上)にわたってウイルスが排出され続けることがあるため、非常に注意が必要な感染源となります。
具体的な感染のシナリオとしては、以下のようなケースが考えられるでしょう。
- 直接接触による感染
- 間接接触による感染
直接接触による感染
これは、健康な犬が感染した犬と直接触れ合うことでウイルスに感染するケースです。
例えば、犬同士が体を寄せ合ったり、じゃれ合ったり、お互いの体を舐め合ったりする行為は、唾液を介してウイルスが伝播する高いリスクを伴います。
また、感染犬の排泄物が付着した被毛を舐めることでも感染は成立します。
ドッグランや公園など、多くの犬が集まる場所では、感染犬との接触の機会が増えるため、特にワクチン接種が完了していない子犬などは注意が求められます。
間接接触による感染
犬アデノウイルス1型は環境中で比較的安定しており、適切な条件下では数週間から数ヶ月生存することが可能です。
そのため、ウイルスに汚染された物や場所を介して感染が広がる間接接触も、主要な感染経路の一つです。
具体的には、感染犬が使用した食器や水飲みボウル、おもちゃ、ベッド、あるいは感染犬の尿や唾液で汚染された地面、床、ケージなどを健康な犬が舐めたり、接触したりすることで感染が起こります。
飼い主の衣服や靴に付着したウイルスが家庭内に持ち込まれ、感染源となる可能性も否定できません。
このように、犬伝染性肝炎は目に見えないウイルスによって、直接的にも間接的にも広がる可能性があるのです。
感染犬の尿には長期間ウイルスが排出され続けるため、回復したように見える犬でも感染源になり得るという点を理解しておくことが重要です。
愛犬を散歩に連れて行く際には、他の犬の排泄物に近づけさせない、地面をむやみに舐めさせないといった基本的な注意が、感染リスクを低減させる上で効果的と言えるでしょう。
感染後の潜伏期間は4日から7日程度
犬が犬アデノウイルス1型に感染してから、実際に症状が現れ始めるまでの期間を「潜伏期間」と呼びます。
犬伝染性肝炎の潜伏期間は、一般的に4日から7日程度とされています。
つまり、ウイルスが体内に侵入してから約1週間は、犬は外見上まったく健康そうに見えるということです。
しかし、この期間中にもウイルスは体内で静かに増殖を続けており、肝臓や血管内皮細胞など、標的となる細胞に次々と感染を広げています。
そして、ウイルスの数が一定量を超え、体の防御機能だけでは抑えきれなくなった時点で、発熱や食欲不振といった最初の症状が姿を現し始めるのです。
この潜伏期間における最も注意すべき点は、症状が出ていないにもかかわらず、感染した犬がすでに他の犬への感染源となり得る可能性があるということです。
ウイルスの排出がいつから始まるかは個体差がありますが、発症直前にはすでに唾液や鼻水などにウイルスが含まれていると考えられています。
そのため、見た目が元気そうだからといって安心はできません。
特に、ワクチン未接種の子犬を新しい環境に迎えた場合や、出所が不明な犬と接触があった場合などは、この潜伏期間を考慮して、数日間は慎重に様子を観察する必要があるでしょう。
また、潜伏期間の長さは、感染したウイルスの量や犬自身の免疫力、年齢、健康状態などによって多少変動することがあります。
免疫力が低い子犬や高齢犬、あるいは何らかの基礎疾患を持つ犬では、潜伏期間が短くなる傾向があるかもしれません。
逆に、非常に少量のウイルスに感染した場合や、ある程度の免疫力を持っている犬では、潜伏期間がやや長引いたり、あるいは症状が非常に軽いために感染に気づかれなかったりするケースも存在します。
潜伏期間中は無症状であるため、感染の発見が遅れがちになる点が、この病気の拡大を防ぐ上での難しさの一つです。
愛犬の様子に少しでも変化が見られた場合は、数日前にどこへ行ったか、どの犬と接触したかなどを思い出し、速やかに動物病院へ相談することが早期発見と早期対応につながります。
子犬は特に重症化しやすく突然死のリスクも
犬伝染性肝炎は、すべての年齢の犬に感染する可能性がありますが、特に生後1年未満の子犬、中でもワクチンプログラムを完了していない若い子犬において、最も重篤な症状を引き起こすことが知られています。
子犬が重症化しやすい理由は、その未熟な免疫システムにあります。
成犬であれば、ウイルスが体内に侵入しても、発達した免疫システムがある程度ウイルスの増殖を抑制し、戦うことができます。
しかし、子犬、特に母犬からの移行抗体(母乳を介して受け継がれる免疫)が少なくなる生後数ヶ月齢の子犬は、ウイルスに対する抵抗力が非常に弱い状態です。
そのため、犬アデノウイルス1型が体内に侵入すると、免疫による抑制がほとんど効かず、ウイルスが爆発的に増殖してしまいます。
この急激なウイルスの増殖は、肝臓の細胞を急速に破壊し、重度の肝不全を引き起こします。
さらに、全身の血管内皮細胞が障害されることで、体のあちこちで出血が起こり、血液凝固異常にも陥ります。
このような深刻な状態が非常に短い時間で進行するため、子犬は「急性」あるいは「劇症」と呼ばれる極めて重い経過をたどることが多いのです。
症状としては、高熱、激しい腹痛、嘔吐、血の混じった下痢などがみられ、急速に衰弱していきます。
そして最も恐ろしいのが、突然死のリスクです。
特に劇症型の場合、飼い主が朝、元気だった子犬の様子を見に行くと、数時間後にはぐったりしており、動物病院に連れて行く間もなく、あるいはほとんど前触れとなる症状を見せることなく亡くなってしまうケースも少なくありません。
これは、重度の肝不全や全身性の出血によるショック状態が、極めて短時間で死に直結するためです。
子犬、特にワクチン未接種の子犬にとって、犬伝染性肝炎は命を直接的に脅かす非常に危険な病気であるという認識が不可欠です。
だからこそ、獣医師の指導のもとで定められたワクチンプログラムを適切な時期に完了させ、十分な免疫を獲得させることが、子犬の命を守る上で何よりも重要となります。
発熱や嘔吐など注意すべき初期症状
犬伝染性肝炎の初期症状は、他の多くの病気の症状と似ているため、見分けるのが難しい場合があります。
しかし、早期に気づき、迅速に獣医療につなげることが重症化を防ぐ鍵となります。
飼い主として知っておくべき、注意すべき初期症状には以下のようなものが挙げられます。
| 症状 | 具体的な様子 |
|---|---|
| 発熱 | 体が熱っぽく、元気がない。食欲が落ちる。犬の平熱は通常38℃台ですが、40℃以上の高熱が出ることが多いです。 |
| 元気・食欲の低下 | いつもはおもちゃで遊ぶのに興味を示さない、散歩に行きたがらない、ぐったりして寝てばかりいるなど、活動性の低下が見られます。食事をほとんど、あるいは全く食べなくなります。 |
| 嘔吐・下痢 | 一度だけでなく、繰り返し吐くことがあります。下痢は水様性で、時には血液が混じり、赤黒いタール状の便(メレナ)が見られることもあります。 |
| 腹痛 | お腹を触られるのを嫌がる、抱き上げようとすると鳴く、背中を丸めてじっとしているといった行動は、腹痛のサインかもしれません。肝臓の腫れによる痛みが多いとされています。 |
| 結膜炎・鼻水 | 目が赤く充血したり、目やにが増えたりします。漿液性(水っぽい)の鼻水やくしゃみなど、風邪のような症状が見られることもあります。 |
| 扁桃の腫れ | 口を開けると喉の奥にある扁桃が赤く腫れているのが確認できる場合があります。 |
これらの症状は、必ずしもすべてが現れるわけではなく、個体によって症状の出方や重症度は異なります。
軽症の場合は、少し元気がない、食欲が落ちるといった程度の症状で回復することもあります。
しかし、これらの症状が複数見られる場合や、特に子犬で急にぐったりし始めた場合には、犬伝染性肝炎の可能性を疑う必要があります。
特に40℃以上の高熱と元気・食欲の消失は、この病気でよく見られる重要なサインです。
愛犬が普段と違う様子を見せた際には、「少し様子を見よう」と自己判断するのではなく、まずはかかりつけの動物病院に連絡し、指示を仰ぐことが大切です。
発熱、元気消失、嘔吐は犬伝染性肝炎の危険なサインであり、見逃さずに早期対応することが求められます。
日頃から愛犬の平熱や普段の食欲、活動量を把握しておくことが、異常の早期発見に繋がるでしょう。
命を守るために知るべき犬伝染性肝炎の原因と対策
◆この章のポイント◆
- 特徴的な症状であるブルーアイについて
- ウイルスに有効な治療法はないのが現状
- 最も効果的な予防はワクチン接種
- 感染拡大を防ぐための具体的な対策
- 犬伝染性肝炎の原因を知り愛犬を守る
特徴的な症状であるブルーアイについて
犬伝染性肝炎の数ある症状の中でも、特に特徴的で「ブルーアイ」として知られているものがあります。
これは、病気の急性期を乗り越え、回復期に入った犬の一部(約20%程度)に見られる眼の症状です。
具体的には、片目または両目の角膜(眼の表面の透明な膜)が青みがかった白色に濁り、まるで青い瞳になったかのように見える状態を指します。
このブルーアイがなぜ起こるのかというと、犬伝染性肝炎の原因である犬アデノウイルス1型に対する体の免疫反応が関係しています。
回復期に入ると、犬の体はウイルスを排除するために抗体を作り出します。
この抗体がウイルスと結合して免疫複合体と呼ばれるものを作ります。
この免疫複合体が眼の中の毛細血管に沈着すると、炎症反応が引き起こされ、その結果として角膜に浮腫(むくみ)が生じます。
角膜は本来、規則正しく並んだコラーゲン線維で構成されているため透明ですが、浮腫によって水分が溜まり線維の並びが乱れることで、光が乱反射し、白く濁って見えてしまうのです。
ブルーアイは通常、急性症状が治まり始めてから1週間から2週間後くらいに突然現れます。
見た目の変化が劇的なため、飼い主は驚くかもしれませんが、多くの場合、この症状は一時的なものです。
通常は1週間から数週間で自然に角膜の濁りが取れて、元の透明な状態に戻ることがほとんどです。
しかし、炎症の程度が強かった場合には、緑内障やぶどう膜炎といったより深刻な眼の病気を続発することもあり、視力に後遺症が残る可能性もゼロではありません。
そのため、ブルーアイの症状が見られた際には、自然に治ることが多いとはいえ、一度動物病院で診察を受け、他に問題が起きていないかを確認してもらうことが推奨されます。
獣医師は、眼の炎症を抑えるための点眼薬などを処方することがあります。
ブルーアイは、犬伝染性肝炎の回復期に見られる特徴的なサインですが、体の免疫がウイルスと戦った証拠でもあります。
現在では混合ワクチンの普及により、犬伝染性肝炎自体の発生が減少しているため、ブルーアイの症状を見る機会も少なくなりましたが、この病気を診断する上での重要な手がかりの一つであることに変わりはありません。
ウイルスに有効な治療法はないのが現状
犬伝染性肝炎と診断された場合、飼い主が最も知りたいのはその治療法でしょう。
しかし、残念ながら2025年現在、犬伝染性肝炎の原因である犬アデノウイルス1型を直接攻撃して体内から排除できるような、特異的な抗ウイルス薬は存在しません。
これは、インフルエンザに対するタミフルのような薬がないことを意味します。
そのため、動物病院で行われる治療は、ウイルスによって引き起こされる様々な症状を和らげ、犬自身の免疫力がウイルスに打ち勝つのを助けるための「対症療法」あるいは「支持療法」が中心となります。
具体的にどのような治療が行われるかは、犬の症状の重症度によって異なりますが、主には以下のような治療法が組み合わせて選択されます。
- 輸液療法
- 抗生物質の投与
- 栄養補給
- 対症療法薬の投与
- 輸血
まず、嘔吐や下痢によって失われた水分と電解質を補給し、脱水症状を改善するための輸液療法は非常に重要です。
また、ウイルス感染によって体の抵抗力が落ちると、細菌による二次感染を起こしやすくなるため、それを防ぐ目的で広域スペクトルの抗生物質が投与されることが一般的です。
肝臓が大きなダメージを受けているため、肝臓の機能をサポートする薬(肝庇護剤)や、吐き気を抑える薬(制吐剤)、下痢を止める薬(止瀉薬)なども症状に応じて使用されます。
重度の出血や貧血が見られる場合には、失われた血液を補うために輸血が必要になることもあります。
自力で食事をとることができない犬に対しては、静脈からの栄養補給や、鼻から胃へチューブを入れて流動食を投与するといった方法で、体力を維持するための栄養管理が行われます。
これらの治療は、あくまで犬が自力で回復するまでの時間を稼ぎ、体を支えるためのものであり、治療の成否は最終的に犬自身の体力と免疫力にかかっています。
だからこそ、特に免疫力の弱い子犬にとっては非常に厳しい戦いとなるのです。
特効薬がないという事実は、この病気の予防がいかに重要であるかを物語っています。
最も効果的な予防はワクチン接種
犬伝染性肝炎は、一度発症すると有効な治療法がなく、特に子犬にとっては命の危険が非常に高い病気です。
しかし、この恐ろしい病気には、極めて効果的な予防法が存在します。
それが、ワクチン接種です。
ワクチン接種は、犬伝染性肝炎から愛犬を守るための、最も確実で重要な手段と言えるでしょう。
現在、日本で一般的に使用されている犬の混合ワクチンには、犬伝染性肝炎の予防成分が含まれています。
これは「コアワクチン」と呼ばれ、生活環境にかかわらず、すべての犬が接種すべき重要なワクチンの一つとして位置づけられています。
多くの混合ワクチンでは、前述の通り、犬アデノウイルス1型(CAV-1)と交差免疫を持つ犬アデノウイルス2型(CAV-2)が使用されています。
CAV-2は呼吸器系の病気の原因ウイルスですが、これに対する免疫を獲得することで、犬伝染性肝炎の原因であるCAV-1の感染も防ぐことができるのです。
ワクチン接種の一般的なスケジュールは以下のようになっています。
子犬のワクチンプログラム
子犬は、母犬の母乳を介して病気に対する免疫(移行抗体)を受け継いでいます。
しかし、この移行抗体は生後6週齢頃から徐々に減少し始め、生後16週齢頃にはほとんどなくなってしまいます。
この移行抗体が存在する間は、ワクチンを接種しても抗体の効果が十分に得られないため、移行抗体がなくなる時期に合わせて、複数回のワクチン接種が必要となります。
一般的には、生後6~8週齢で1回目の接種を開始し、その後は3~4週間隔で2~3回の追加接種を行い、生後16週齢以降に最終接種を終えるのが標準的なプログラムです。
成犬の追加接種(ブースター接種)
子犬の時期に確立された免疫も、時間とともに少しずつ低下していきます。
そのため、免疫力を高いレベルで維持するために、成犬になってからも定期的な追加接種が必要です。
以前は毎年の追加接種が推奨されていましたが、近年の研究により、コアワクチンの免疫持続期間は3年以上であることがわかってきました。
そのため、現在では3年に1回の追加接種を推奨するガイドラインが主流となっています。
ただし、最適な接種間隔は犬の年齢や健康状態、生活環境によって異なるため、必ずかかりつけの獣医師と相談して決定することが重要です。
ワクチン接種を適切に行うことで、犬伝染性肝炎の発症をほぼ100%防ぐことが可能です。
ワクチンの普及により、この病気の発生は劇的に減少しましたが、それは多くの飼い主がワクチン接種の重要性を理解し、実践してきた結果です。
油断することなく、愛犬のために定められたワクチンプログラムを必ず完了させましょう。
感染拡大を防ぐための具体的な対策
ワクチン接種が犬伝染性肝炎の最も重要な予防策であることは間違いありませんが、それに加えて、日常生活の中で感染拡大を防ぐための対策を講じることも大切です。
特に、多頭飼育の家庭や、新しく犬を迎え入れる際には、以下の点に注意することで、リスクを最小限に抑えることができます。
ワクチンプログラム完了前の社会化
子犬の社会化期(生後3週齢~16週齢頃)は、他の犬や人、様々な環境に慣れさせる上で非常に重要な時期です。
しかし、この時期はまだワクチンプログラムが完了しておらず、感染症に対する抵抗力が不十分な状態でもあります。
そのため、不特定多数の犬が集まるドッグランや公園に連れて行くのは避けるべきでしょう。
社会化のためには、ワクチン接種歴が明確で、健康であることが確認されている犬と、管理された安全な環境で接触させるのが理想的です。
パピークラスなどに参加する際も、施設の衛生管理や参加犬の健康状態について事前に確認することが重要です。
環境の消毒
犬アデノウイルス1型は、アルコール消毒などでは効果がなく、環境中で長く生存する比較的強いウイルスです。
もし、家庭内で犬伝染性肝炎の発生が疑われる、あるいは確定した場合には、ウイルスの拡散を防ぐために徹底した消毒が必要になります。
このウイルスに有効な消毒薬としては、次亜塩素酸ナトリウム(家庭用塩素系漂白剤を希釈したもの)や、グルタルアルデヒド、第四級アンモニウム塩などが挙げられます。
犬が使用した食器、ケージ、おもちゃ、床などをこれらの消毒薬で丁寧に清拭・洗浄します。
ただし、これらの消毒薬は犬の体や粘膜に刺激を与える可能性があるため、使用方法をよく守り、消毒後は十分に水拭きや乾燥を行う必要があります。
新しく迎える犬の健康チェック
新しく保護犬やペットショップから犬を迎え入れる際には、その犬のワクチン接種歴を必ず確認しましょう。
可能であれば、家庭に迎える前に動物病院で健康診断を受け、潜伏期間の可能性も考慮して、最初の数週間は先住犬との接触を慎重に行うのが安全です。
感染症の知識を持ち、衛生管理を徹底することが、愛犬だけでなく他の犬たちへの感染拡大を防ぐ社会的な責任にも繋がります。
日々の生活の中で、愛犬の健康を守るための意識を高く持つことが大切です。
犬伝染性肝炎の原因を知り愛犬を守る
ここまで、犬伝染性肝炎の原因から症状、そして治療と予防法について詳しく解説してきました。
この病気の原因は犬アデノウイルス1型という特定のウイルスであり、感染犬の尿や唾液を介して広がります。
特にワクチン未接種の子犬が感染した場合には、突然死に至ることもあるほど重症化しやすく、非常に危険な病気です。
回復期にはブルーアイという特徴的な眼の症状が見られることもありますが、そもそもこの病気にはウイルスを直接退治する特効薬が存在しません。
治療は、犬自身の免疫力がウイルスに打ち勝つまでの時間を稼ぐための対症療法に限られます。
だからこそ、私たち飼い主にできる最大かつ最善の防御策は、ワクチン接種による予防に他なりません。
適切にワクチンを接種していれば、犬伝染性肝炎の発症はほぼ確実に防ぐことができます。
愛犬の命と健康を守るために、獣医師と相談の上で適切なワクチンプログラムを必ず完了させることが、飼い主の重要な責任と言えるでしょう。
犬伝染性肝炎の原因を正しく理解し、予防の重要性を認識することが、愛犬と一日でも長く、健やかな毎日を送るための礎となります。
本日のまとめ
- 犬伝染性肝炎の原因は犬アデノウイルス1型である
- ウイルスは肝臓や全身の血管に深刻なダメージを与える
- 主な感染経路は感染犬の尿や唾液との接触
- ウイルスで汚染された物を介した間接感染にも注意が必要
- 感染後の潜伏期間は約4日から7日
- 子犬は免疫力が低いため重症化しやすく突然死のリスクがある
- 初期症状は発熱や嘔吐など他の病気と見分けがつきにくい
- 回復期に角膜が白濁するブルーアイが見られることがある
- ウイルスを直接攻撃する特異的な治療法は存在しない
- 治療は犬自身の免疫力を助ける対症療法が中心となる
- 最も効果的で確実な予防法はワクチン接種である
- 混合ワクチンに含まれるコアワクチンで予防が可能
- 子犬の時期に適切な回数のワクチン接種を完了させることが重要
- 成犬も定期的な追加接種で免疫を維持する必要がある
- 正しい知識を持つことが愛犬を恐ろしい病気から守る第一歩となる

愛犬の「食べない」に終止符を。手作り食レシピから生まれた『モグワン』
「せっかく買ったフードを食べてくれない…」そんな悩みを抱えていませんか?
『モグワン』は、愛犬の健康と食いつきの良さをとことん追求し、家庭での手作りごはんをヒントに誕生したプレミアムドッグフードです。
【モグワンが選ばれる3つの理由】
- 動物性タンパク源50%以上:新鮮なチキンとサーモンを贅沢に使用。封を開けた瞬間の香りが、愛犬の食欲を刺激します。
- 究極のグレインフリー:消化に負担をかける穀物を一切使わず、お腹にやさしいレシピを実現しました。
- ヒューマングレードの原材料:人間が食べる食材と同等の高品質な素材を厳選。着色料や香料も不使用で安心です。
毎日のごはんは、愛犬の体を作る大切な基盤。 「美味しそうに完食する姿が見たい」という飼い主さんの願いを、モグワンが叶えます。
今なら公式サイト限定の特別キャンペーンも実施中!まずは愛犬の驚くべき「食いつき」を体験してみませんか?
参考サイト
犬伝染性肝炎 – ハートワン動物病院総合医療ケアセンター – 東京都 豊島区 池袋
犬の病気犬伝染性肝炎 – 日本臨床獣医学フォーラム
【犬が下痢をした。原因は?】犬伝染性肝炎というウイルス感染症を獣医師が解説します。 – 日本橋動物病院
犬伝染性肝炎ってどんな病気?症状や原因、予防法を解説 | EPARKペットライフ
犬伝染性肝炎 | 病院だより | 京都市左京区の動物病院「かく動物病院」
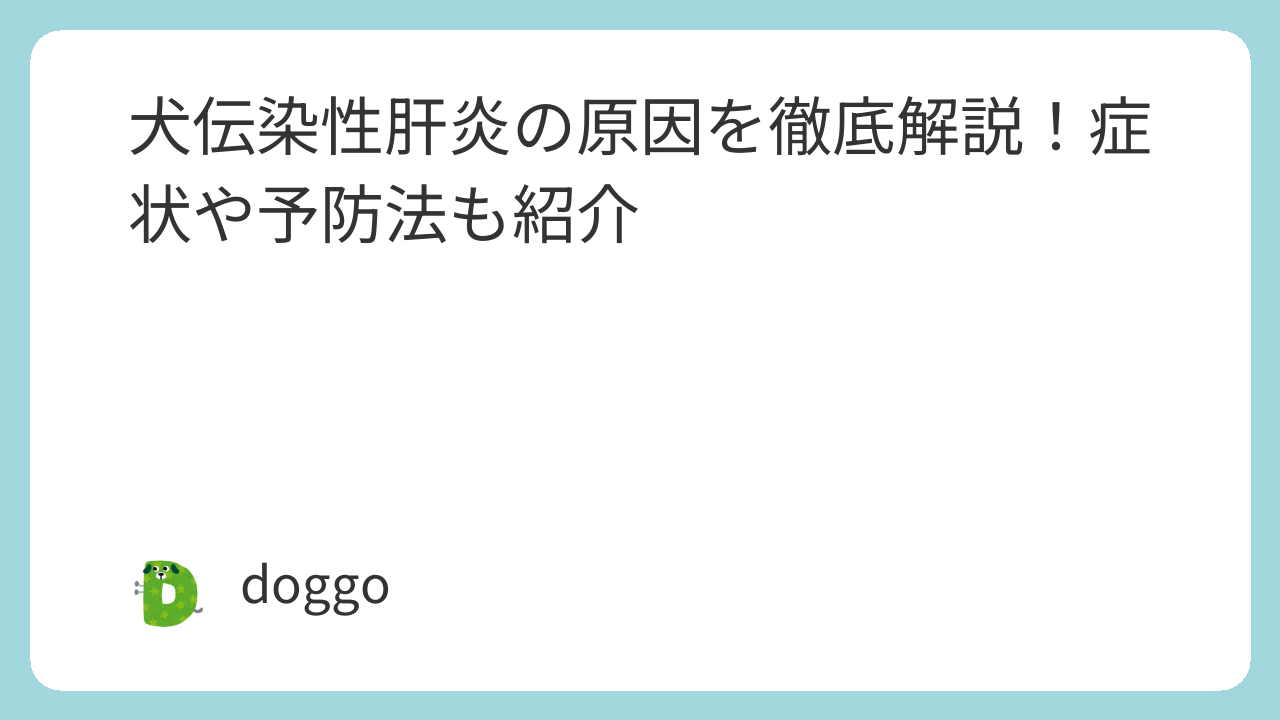
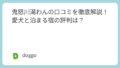
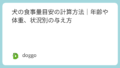
コメント